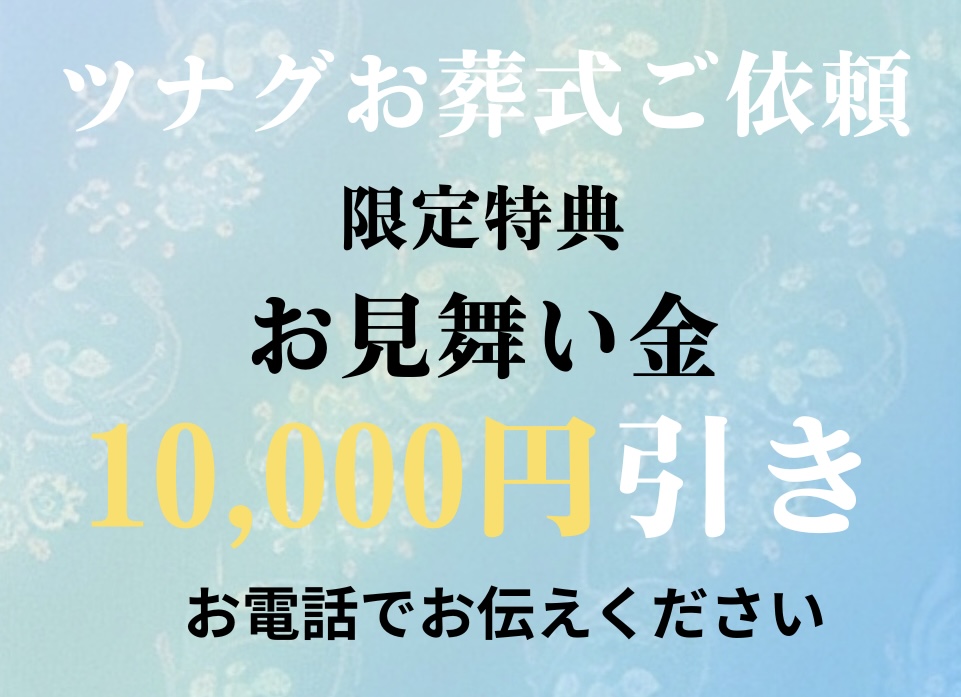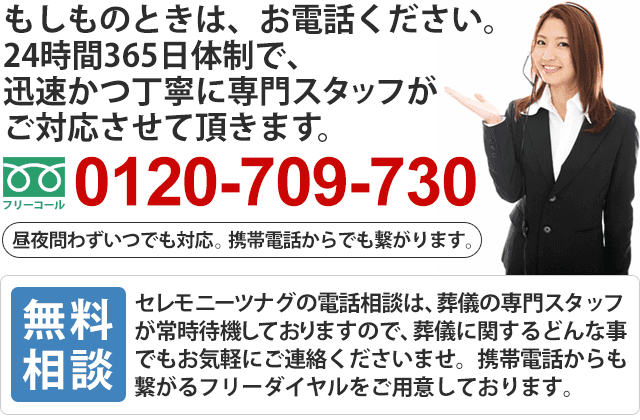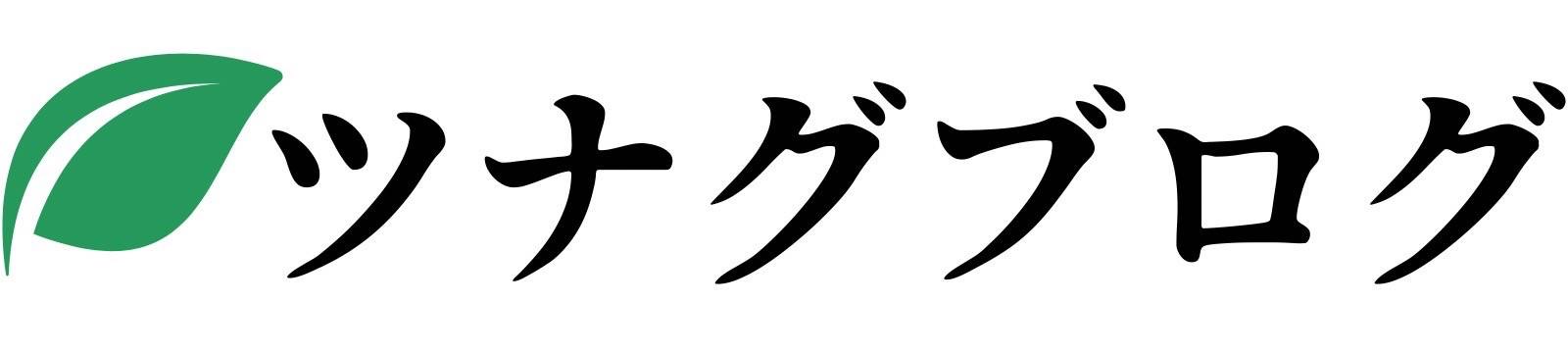24時間365日 無料で相談する
弔電にプリザーブドフラワーは迷惑?プロが解説

弔電にプリザーブドフラワーを添えるのは迷惑ではないかと、心配になって検索されたのではないでしょうか。
弔電用のプリザーブドフラワーをお供えとして贈るべきか、生花ではなく仏壇用のプリザーブドフラワー仏花を選んでも失礼にならないのか、初盆のお供えや法要・法事で枯れないお花を贈るのはどうなのかなど、細かな点が気になってしまいますよね。普段はあまり意識しない分、いざというときに「本当にこれで合っているのかな」と不安になりやすいところだと思います。
実際の現場でも、お悔やみ電報としての弔電とプリザーブドフラワーのセットが届いたとき、「ありがたいけれど荷物が増えて負担だった」と感じる遺族もいれば、「通夜や告別式のあとも長く飾れてうれしかった」と喜ばれるケースもあります。
家族葬で弔電や供花をどうするか、葬儀後に仏壇へ供えるプリザーブドフラワー仏花を贈るべきか迷う声も少なくありませんし、「そもそも弔電は送らない方がいい?」と、根本的なところから相談を受けることもあります。
このコラムでは、西宮市で家族葬や一般葬をお手伝いしているセレモニーツナグの立場から、弔電にプリザーブドフラワーを添える行為が本当に迷惑になる場面と、むしろ助けになる場面を、遺族と送る側の両方の目線でお話しします。
あわせて、弔電用プリザーブドフラワーのお供えを選ぶときのマナーや注意点、「送らない方が良かったのでは」と後悔しないための考え方も整理していきますので、この記事だけで一通りイメージがつかめるはずですよ。
費用感やマナーには地域差があり、「これだけが正解」という絶対のルールはありません。
この記事を読みながら、ご自身と故人・ご遺族との関係性、葬儀の規模、家族葬かどうかといった事情を思い浮かべていただくことで、より納得感のある判断ができるはずです。迷っている気持ちごと、ここで一度整理してみてくださいね。
- プリザーブドフラワー付き弔電が迷惑と言われる理由と実情
- 遺族に喜ばれるプリザーブドフラワーの特徴と選び方
- 弔電のプリザーブドフラワーを迷惑にしないマナーと注意点
- よくある疑問と後悔しないための判断のポイント
弔電にプリザーブドフラワーは迷惑?現場の本音
まずは、「弔電 プリザーブドフラワー 迷惑」と検索したくなる背景と、実際の葬儀現場でどのように受け止められているのかを整理しておきましょう。
弔電そのものはありがたい一方で、付いてくる品物が負担になることもあり、そのギャップが不安の正体なんですよね。「気持ちは伝えたいけれど、相手にとって重荷にはなりたくない」という、あなたの優しさからくる迷いだと思います。
弔電にプリザーブドフラワーを添える人の不安
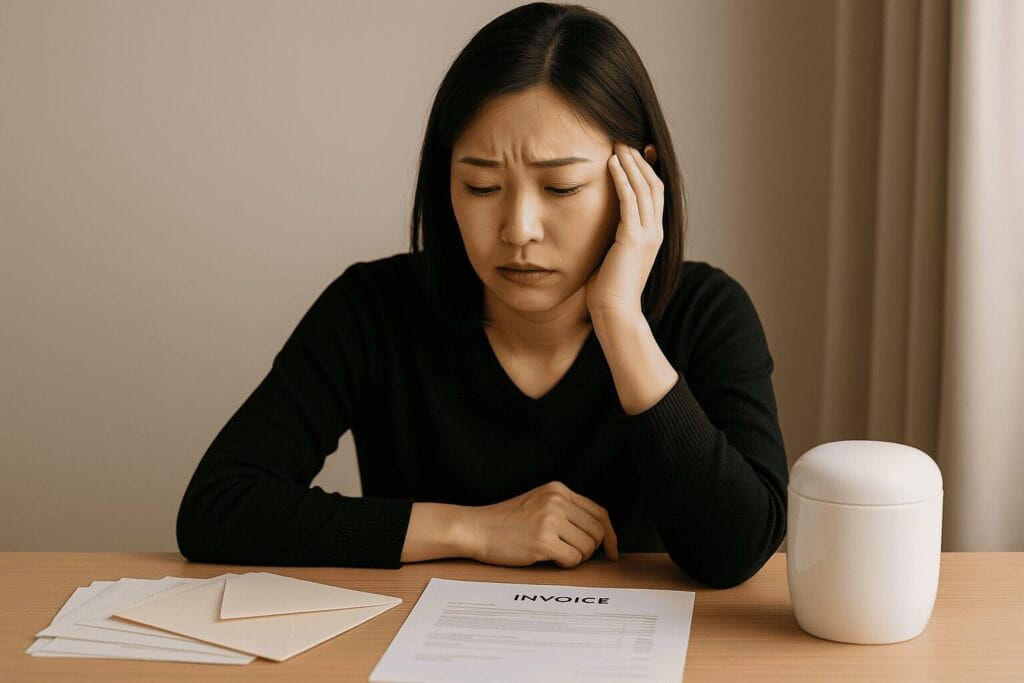
弔電にプリザーブドフラワーを添えようとする方の多くは、参列できない代わりに少しでも気持ちを形にしたいという思いをお持ちです。同時に、
- 生花ではなくプリザーブドフラワーで本当に良いのか
- 弔電用のプリザーブドフラワーお供えはマナー違反にならないか
- 遺族から「荷物が増えて迷惑」と思われないか
- 家族葬で弔電まで送るのは重たく受け取られないか
といった点に不安を感じています。ここ、すごく気になりますよね。葬儀はどうしても「マナー」「常識」という言葉が頭をよぎる場面なので、ふだん以上に慎重になってしまうのは自然なことです。
さらに、「周りの人はどうしているんだろう」「ネットの意見が真逆で余計にわからなくなった…」という声もよく聞きます。とくにプリザーブドフラワーは新しいスタイルなので、親世代・祖父母世代の感覚と、あなた自身の感覚が微妙にズレていることも多いんですよね。そのズレが「本当に大丈夫かな?」というモヤモヤにつながっているのかなと思います。
葬儀の現場にいると、こうした「失礼にならないか」という気遣いからご相談をいただくことが本当に多く、皆さんが真剣に悩まれていることを肌で感じます。「この選択で、ご遺族が少しでもホッとしてくれたらいいな」という気持ちさえあれば、あとはポイントさえ押さえれば大きく外すことはありませんので、一つずつ整理していきましょう。
遺族から見て負担になりやすいポイント

「弔電 プリザーブドフラワー 迷惑」と言われやすいのは、決して気持ちが迷惑なのではなく、いくつかの実務的な負担があるためです。代表的なポイントを整理します。「現場で何が起きているか」を知ると、どこに気を付ければいいのかがかなり見えてきますよ。
遺族の負担になりやすい理由
- 弔電とプリザーブドフラワーが別々に飾られ、誰からの品物かわかりにくい
- 陶器入りなど重くてかさばるタイプは、遺影や骨壺と一緒に持ち帰るとき荷物が増える
- 家族葬や小規模葬で「できるだけ簡素に」と考えている遺族には、豪華な品物が負担に感じられる
- プリザーブドフラワーの雰囲気を「命のない花」と捉えて好まない方も一部にいる
特に、遺族が会場から帰るときの荷物の多さは、実際にお手伝いをしているとよくわかります。遺影、位牌、骨壺、書類一式、ご厚志の品などを抱えて移動する中で、大きなプリザーブドフラワーがいくつもあると「ありがたいけれど持ち切れない」という状況になりがちです。
車で来られているご家族ばかりではありませんし、電車移動の方やご高齢の方も多いので、物理的な負担はかなり現実的な問題なんですよね。
また、弔電の本文とプリザーブドフラワー本体が別々の場所に置かれることも多く、「このお花、どなたからいただいたんだろう?」とわからなくなってしまうケースもあります。せっかく選んでくださったのに、贈り主がわからないままだと、ご遺族としても少しもやっとしてしまうところです。
こうした現場の事情から、商品付きの弔電が「はっきり言って迷惑」と表現されることもありますが、それはあくまで「選び方次第で負担になりやすい」という現象を指しています。逆に言えば、サイズ感やデザイン、タイミングなどを意識すれば、「ありがたい」と感じてもらえる方向にもきちんと持っていけるということです。
実際には喜ばれるプリザーブドフラワーも多い

一方で、プリザーブドフラワー付きの弔電が喜ばれるケースも少なくありません。むしろ、私が現場で見ている限りでは、配慮して選ばれたプリザーブドフラワーは好意的に受け止められることが多い印象です。「なんだ、プリザーブドもアリなんだ」と安心される方も多いですよ。
プリザーブドフラワーが喜ばれる理由
- 水やり不要で長く飾れるため、初七日から四十九日、自宅での後飾りに重宝する
- 生花と違ってすぐに萎れないので、忙しい遺族の手間を減らせる
- 花粉が出ないため、室内や仏壇まわりを清潔に保ちやすい
- ガラスケース入りやフォトフレーム付きなど、インテリアとしても使いやすい
とくに仏壇用プリザーブドフラワー仏花のような、落ち着いた色合いでコンパクトなアレンジは、「葬儀後の仏壇が寂しくならず助かった」と感謝されることがよくあります。頻繁にお花を買いに行く余裕がないご家庭にとっては、「いつ見てもきれい」というのはかなり心強いポイントなんですよね。
生花とプリザーブドの違いイメージ
| 項目 | 生花 | プリザーブドフラワー |
|---|---|---|
| 持ち | 数日〜1週間ほど | 数カ月〜数年ほど |
| お手入れ | 水替え・花瓶の洗浄が必要 | 基本的に手入れ不要、ホコリを払う程度 |
| 見た目の変化 | 徐々にしおれていく | 大きな変化が少ない |
| 宗教的イメージ | 伝統的でオーソドックス | 新しさがあり、感じ方に個人差あり |
あくまで一般的なイメージですが、それぞれの特徴を知っておくと、どちらを選ぶか考えやすくなります。
「迷惑かどうか」は、プリザーブドフラワーそのものよりも、サイズ・デザイン・贈るタイミング・遺族の方針との相性で大きく変わるというのが、葬儀現場での実感です。だからこそ、「プリザーブドだから即NG」と決めつける必要はなく、「相手の状況に合うかどうか」で考えてみるのがおすすめですよ。
供花や仏花として贈るときの考え方

最近は、供花としてプリザーブドフラワーを選ぶ方も増えています。仏壇用のプリザーブドフラワー仏花や、初盆のお供えとしてのプリザーブドフラワーアレンジなど、いわゆる「枯れないお花」は、多忙なご家庭や高齢のご遺族にとって扱いやすい選択肢です。水換えの必要がないので、体力的な負担が少ないのも大きいですね。
ただし、スタンド花のような大きな供花をプリザーブドで贈るのは、祭壇スペースの都合や宗派・地域の慣習により好まれない場合もあります。「会場はこじんまりと」と考えているところに巨大な花が届いてしまうと、置き場所に困ってしまうことも。弔電に添えるプリザーブドフラワーは、あくまで「仏壇や後飾りに置きやすいサイズ」を意識して選ぶのがおすすめです。
供花としてのプリザーブドフラワーのポイント
- 白や淡い色味を基調にした落ち着いたデザインを選ぶ
- 仏壇に収まりやすい高さ・奥行きかをイメージする
- スペースが限られる自宅葬やマンション住まいでは特にコンパクトなものを
- 花器の素材(ガラス・陶器など)が重すぎないかもチェックする
また、「初盆に合わせて改めてプリザーブドフラワーを送りたい」というご相談も多いです。初盆は特別な節目なので、そこで少し華やかなものを、というのはよくある考え方です。ただ、その場合も「今、仏壇やお家のスペースにどれくらい物が置いてあるかな?」とイメージしてみてください。すでにたくさんのお供えやお花が並んでいるようなら、コンパクトなサイズや壁掛けタイプなども選択肢になります。
なお、地域によっては供花そのものを辞退されることもあります。その場合は、無理にプリザーブドフラワーを贈らず、手紙や香典など別の形で気持ちを伝える方が穏当です。「送りたい気持ち」と「相手の負担にならないか」のバランスをとりながら、柔軟に考えていきましょう。
家族葬など小さな葬儀での注意点

家族葬や直葬など、小規模なお別れの場では「静かに見送りたい」「負担を減らしたい」という遺族の意向が強い傾向があります。そうした場で、豪華なプリザーブドフラワー付き弔電がいくつも届くと、ありがたい一方で「お返しやお礼をどうしよう」と頭を抱えてしまうご家族も少なくありません。ここは本当にデリケートなところです。
ツナグブログでも、家族葬に呼ばれていないときの振る舞いについては詳しく解説しています。家族葬での香典や供花・弔電の考え方が気になる方は、家族葬に呼ばれていないときの対応と香典・供花のマナーも参考になるはずです。家族葬は「小さく」「シンプルに」を望まれているケースが多いので、その流れに沿った弔意の伝え方を意識してみてください。
家族葬で弔電を送るか迷ったときは、
- 案内状に「弔電・供花はご辞退申し上げます」といった記載がないか
- 遺族が「本当に身内だけで」と強調していたかどうか
- 自分が香典やお悔やみの手紙など、他の方法で気持ちを伝えられるか
といった点を踏まえて、「どの形がいちばん相手にとって負担が少ないか」を軸に考えてみてください。たとえば、遠方からの友人であれば、弔電ではなく、少し時間をおいてからお悔やみの手紙を送る方が、ご家族の気持ちに寄り添えることもあります。
また、最近はウェブ葬儀や小規模葬をめぐる料金トラブルも社会問題になっています。葬儀の負担感は、金額や手続きの複雑さとも強く結びついているので、「相手の負担を増やさない」という視点はとても大事です。
葬儀費用やトラブルの傾向については、独立行政法人国民生活センターでも情報がまとめられていますので、全体感を知りたい方はチェックしてみても良いと思います(出典:国民生活センター「大切な葬儀で料金トラブル発生!」)。
弔電のプリザーブドフラワーを迷惑にしないマナー
ここからは、実際にプリザーブドフラワー付きの弔電を送ると決めたときに、迷惑になりにくい選び方・送り方のポイントを整理していきます。細かなマナーにとらわれ過ぎる必要はありませんが、いくつかの基本を押さえておくと安心です。「ここだけ押さえておけば大丈夫」という軸を作ってあげるイメージですね。
弔電を送る前に必ず確認したいこと
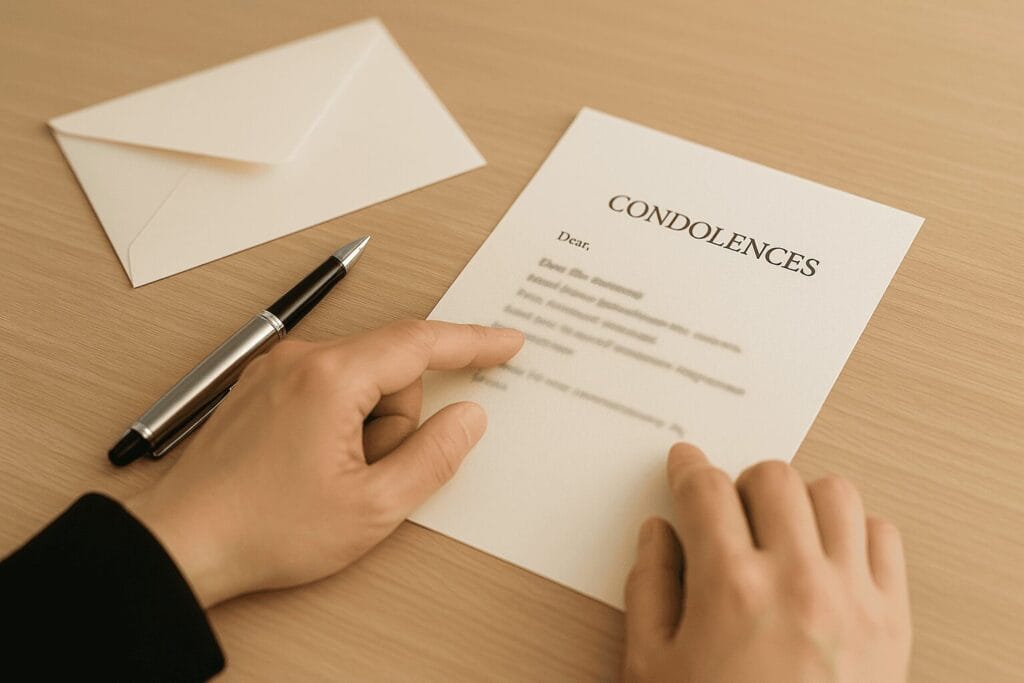
もっとも大切なのは、遺族の意向を尊重することです。訃報や葬儀案内の中に、
- 「ご香典・ご供花・弔電は固くご辞退申し上げます」
- 「勝手ながら御供物等は辞退させていただきます」
といった文言がある場合は、たとえプリザーブドフラワーであっても、弔電や贈り物は控えるのがマナーです。「せっかく用意したのに…」と思うかもしれませんが、その一文には「お気持ちだけいただきますので、どうかお気遣いなさらないでください」というご家族の思いが込められていることが多いんですね。
送る前のチェックリスト
- 訃報メールや案内状に「辞退」の一文がないか、最後まで読み直したか
- 家族葬や直葬で、遺族が範囲をかなり絞りたい意向ではないか
- 弔電が通夜・葬儀に間に合うタイミングで手配できるか
- 弔電ではなく、手紙や香典の方が自然な関係性ではないか
- 以前、同じご家族のときにどういったやり取りをしたか覚えているか
どうしても判断に迷う場合は、共通の知人に相談したり、喪主に近いご家族に「弔電をお送りしてもよいでしょうか」と一言伺ってからにすると、行き違いを防ぎやすくなります。直接聞くのは気が引けるかもしれませんが、「迷ったまま自己判断で動く」よりも、ずっと親切な選択になることも多いですよ。
もうひとつ大事なのは、「本当に弔電という形がベストか?」を一度立ち止まって考えてみることです。たとえば、
- 後日ゆっくりお宅を訪問できる関係性なら、訪問時の手土産に想いを込める
- 気軽に連絡を取り合える間柄なら、数日おいてからお悔やみの手紙を出す
といった選択肢もあります。弔電が「唯一の正解」ではありませんので、相手と自分の距離感に合った形を探してみてくださいね。
色合い・サイズ・デザイン選びのコツ

プリザーブドフラワーは、選び方で印象が大きく変わります。弔電用としては、祝い事向けとはまったく違う視点で選ぶことが大切です。「かわいい」「映える」ではなく、「落ち着いていて、そっと寄り添ってくれる感じ」がキーワードだと思ってください。
- 色は白・クリーム・淡い紫・淡いグリーンなど落ち着いたトーンを中心に
- 真紅のバラやカラフルなアレンジは、四十九日までの期間は避ける
- 仏壇や後飾り壇に置きやすい、小ぶりで安定感のあるサイズにする
- ホコリを防げるガラスケース入りやボックス型は、管理が楽で喜ばれやすい
たとえば、丸いドーム型のプリザーブドフラワーは、倒れにくくホコリもかぶりにくいので、仏壇まわりに置くにはとても扱いやすいです。一方、細長い一輪挿しスタイルなどは見た目は素敵ですが、地震やちょっとした振動で倒れやすいこともあるので、慎重に選びたいところですね。
また、複数の人が線香付き弔電やロウソク付き弔電を選ぶと、遺族が「こんなにたくさんどうしよう」と困ってしまうこともあります。オプション品を増やすほど荷物も増えますので、
「豪華さ」ではなく「扱いやすさ」と「飾りやすさ」を重視して選ぶことを意識してみてください。豪華さを出したいときは、値段を上げるよりも、「メッセージを丁寧に書く」「故人との思い出を一行添える」といった方向に力を入れる方が、ご遺族の心には響きやすいですよ。
宗教や地域の習慣への配慮

日本の葬儀は宗派や地域差が大きく、花の扱いも一様ではありません。一般的には仏式の葬儀が多く、白い菊やユリなどの生花が基本ですが、最近はプリザーブドフラワーやアートフラワーを受け入れるご家庭も増えています。「昔ながらのスタイル」を大切にされる地域もあれば、「あまり形式にはこだわらないので好きな花を」というご家庭もあり、本当にさまざまです。
注意したいのは、
- 「とげのある花は避けた方がよい」と考える方が今も一定数いること
- 浄土真宗など一部の宗派では、「冥福」などの言葉選びに敏感な方もいること
多くのプリザーブドフラワーにはバラが使われますが、加工の段階でとげは取り除かれていることがほとんどです。それでも気になる場合は、菊やカーネーション、蘭などを中心にしたデザインを選ぶと安心です。どうしても迷うときは、「お供え用」「仏花用」と明記されている商品を選ぶと、ある程度は安心感が増しますよ。
宗派や地域の細かな違いについて不安がある場合は、葬儀社や菩提寺など、事情をよく知る専門家に相談するのがいちばん確実です。ここでお伝えしている内容はあくまで一般的な目安であり、正確な情報は公式サイトや宗派の案内なども確認し、最終的な判断は専門家にご相談ください。とくに神道やキリスト教式など、仏式以外の葬儀では考え方が変わる部分もあるので、「なんとなく」で決めずに一度立ち止まるのがおすすめです。
弔電の文面と宛名の整え方
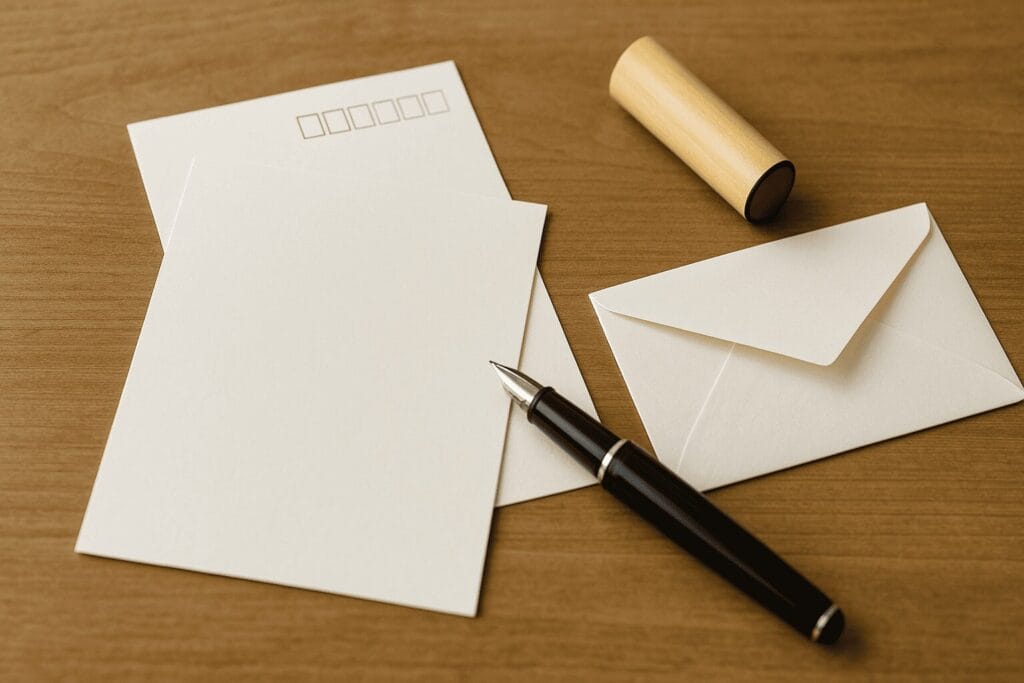
プリザーブドフラワー付きかどうかに関わらず、弔電でいちばん大切なのは文面と宛名です。どれほど立派な台紙や花を選んでも、文章がそっけなかったり宛名が曖昧だと、気持ちが十分に伝わりません。逆に、シンプルな台紙でも、文面が丁寧であればそれだけで十分な弔意になります。
宛名の基本
弔電の宛名は、原則として喪主のお名前にします。喪主名がわからない場合は、わかっている範囲で
- 「〇〇様 ご遺族様」
- 「故〇〇〇〇様 ご遺族一同様」
といった書き方にすることもあります。差出人欄には、氏名だけでなく「〇〇株式会社 △△部」「〇〇大学〇年卒業生」など、故人との関係がわかるように添えておくと、ご遺族が整理しやすくなります。「誰の関係先なのか」がはっきりしていると、お礼状を書くときもスムーズなんですよね。
文面のポイント
文面では、
- 病気の細かな内容や死因には触れない
- 「重ね重ね」「またまた」などの重ね言葉(忌み言葉)を避ける
- 句読点を打たない形式にする(弔電の慣習)
といった基本を押さえておくと安心です。弔意の表現について詳しく知りたい方は、ご冥福をお祈りしますの正しい使い方と文例も参考にしていただけます。言葉づかいに迷ったときに、一度目を通しておくと安心感が違いますよ。
弔電文面のひな型イメージ
このたびはご尊父様のご逝去の報に接し謹んでお悔やみ申し上げます
長年のご厚情に深く感謝いたしますとともに安らかなご永眠をお祈りいたします
文例はあくまで一例であり、故人との関係性やご自身の言葉を少し加えると、より心のこもった弔電になります。「学生時代から大変お世話になりました」「いつも明るく声をかけてくださったことを思い出します」など、一行でも具体的なエピソードが入ると、ご遺族にとってはとてもあたたかいメッセージになります。
よくある質問と後悔しないための判断軸

ここからは、お客さまから特に多くいただく質問をまとめてお答えします。弔電そのものが迷惑にならないか、家族葬ではどうしたらよいかといった具体的な不安を整理していきましょう。「これ、自分も気になっていた」というポイントがきっとあると思います。
Q1. 弔電を送ること自体が迷惑になることはありますか?
弔電は、本来ご遺族を慰めるためのものですから、基本的には迷惑ではありません。「遠方からでも気にかけてくれているんだな」と、後から読み返して涙ぐまれるご家族も多いです。ただし、案内状で弔電や供花の辞退が明記されている場合や、「身内だけで静かに送りたい」という意向がはっきり示されている場合は、送らない方がよいでしょう。
また、故人や遺族との接点がほとんどない場合に、形式的な弔電だけを送ると「かえって気を遣わせてしまった」と感じさせる可能性もあります。このあたりは、人間関係や会社の慣習なども関わってきますが、関係性や距離感をふまえ、「本当に自分から弔電を送るのが一番自然か」を考えてみてください。
Q2. 家族葬では弔電を送らない方がよいのでしょうか?
家族葬だから弔電が禁止される、という決まりはありません。むしろ、参列できない方からの弔電は、後でじっくり読み返せる慰めになることも多いです。ただし、家族葬は招く人を絞る前提のため、遺族の意向がより強く反映されます。
案内状の文面を確認したうえで、それでも不安があれば、先ほどご紹介した家族葬の記事や、お通夜とお葬式どちらを優先すべきかを解説したコラムも参考にしながら、全体のバランスを考えてみてください。どうしても迷うときは、「今回は弔電ではなく、少し時間を置いたお悔やみの手紙にしよう」といった選び方もアリだと思います。
Q3. 供花としてプリザーブドフラワーを贈るのは失礼ですか?
色合いとデザインが弔事にふさわしいものであれば、失礼にあたることはほとんどありません。むしろ、忙しいご家庭や高齢のご遺族には、生花よりも「枯れないお花」の方が扱いやすいという声も多く聞きます。水換えの必要がなく、花びんの置き場所も選ばないので、「置きっぱなしにしても傷みにくい」というメリットもあります。
ただし、大きなスタンド花や大量のアレンジを独断で贈るのは、スペースやお返しの面で負担になることがあります。供花全般に言えることですが、事前に「お花をお贈りしてもよろしいでしょうか」と一言確認するだけで、トラブルはぐっと減ります。「お気持ちだけで十分です」と言われたら、その言葉を尊重することも大切なマナーですね。
Q4. プリザーブドフラワーをもらって困るケースはありますか?
正直なところ、「ありがたいけれど少し困った」という声もゼロではありません。典型的なのは、
- プリザーブドフラワーの捨てどきがわからず、処分に迷ってしまう
- 仏壇や部屋が狭く、置き場所に困る
- 本人は生花が好きで、加工花にはあまり惹かれない
といったケースです。ただ、こうした悩みは「絶対に迷惑だからやめてほしい」というものではなく、「大切な品だからこそ扱いに悩む」という性質のものです。「捨ててしまうのは申し訳ないけれど、いつまで置いておくべきなんだろう…」と、むしろ大切に思うからこそ迷ってしまう、という感じですね。
実際のところ
多くのご遺族は、いただいたプリザーブドフラワーを仏壇やリビングにしばらく飾った後、感謝の気持ちとともに整理されています。お焚き上げに出す方もいれば、小さなパーツだけ残して思い出として取っておく方もおられます。「いつまで置かなければいけない」という決まりはありませんので、ご家族なりのタイミングで区切りをつけていただいて大丈夫ですよ。
Q5. 弔電に品物(線香など)を付けるのはマナー違反ですか?
線香やロウソク、プリザーブドフラワーなどを弔電に添えること自体は、マナー違反ではありません。ただ、必須でもありませんし、「付ければ付けるほど良い」というものでもありません。ここは勘違いしやすいところかなと思います。
とくに線香付き弔電が集中すると、ご遺族が「この量を使い切るのはいつになるだろう」と途方に暮れてしまうこともあります。オプション品はあくまで一つ程度にとどめ、
「遺族が無理なく使える量かどうか」「同じような品が重ならないか」を想像することが何よりのマナーです。「自分だったら、どれくらいの量までなら素直にありがたく受け取れるかな?」と、少し想像してみるとイメージしやすいですよ。
Q6. 弔電を送って後悔することはありますか?
「送らない方が良かったかもしれない」と後悔される方の多くは、
- あとから弔電や供花を辞退していた事実を知った
- 葬儀に間に合わず、結果的にタイミングを外してしまった
といったケースです。いずれも、
- 訃報連絡の内容を落ち着いて読み直す
- 日程に余裕がない場合は、無理に弔電にこだわらず、後日お手紙や訪問で弔意を伝える
といった工夫でかなり防ぐことができます。真心を込めて送った弔電であれば、ご遺族が「迷惑だった」と感じることはまれですから、過度に自分を責める必要はありません。「あのときは精一杯だったな」と、ご自身の気持ちも少し優しく振り返ってあげてくださいね。
まとめ:弔電に添えるプリザーブドフラワーを迷惑にしないために
弔電にプリザーブドフラワーを添えるべきかどうか悩むとき、多くの方が心のどこかで「弔電でプリザーブドフラワー を送ると迷惑になる・・・?」という言葉を思い浮かべています。ですが、問題なのはプリザーブドフラワーそのものではなく、
- 遺族の意向や葬儀の方針をどれだけ尊重できているか
- サイズやデザインが負担にならないか
- 文面や宛名が丁寧に整えられているか
といった「送り方」の部分です。ここを丁寧に整えてあげれば、「迷惑」ではなく「ありがたいお気持ち」として受け止めてもらえる可能性はぐっと高まります。
私の感覚では、遺族の立場に立って選ばれたプリザーブドフラワー付き弔電は、むしろ「後飾りや仏壇が寂しくならず心強かった」と喜ばれることが多いと感じています。一方で、豪華さだけを追求した大きなアレンジや、辞退の意向を無視した贈り物は、善意であっても負担になりやすいのも事実です。このあたりのバランス感覚が、「迷惑かどうか」を左右していると言ってもいいかもしれません。
迷ったときは、「自分が遺族の立場だったらどう感じるか」を一度イメージしてみてください。そのうえで、
- 弔電を送るかどうか
- プリザーブドフラワーを添えるか、文章だけにするか
- 別の形(香典・手紙・訪問など)で弔意を伝えるか
を選んでいけば、大きく間違うことはありません。「一番大事なのは、相手の心に寄り添おうとする気持ち」だということを、どうか忘れないでいてくださいね。
ここでご紹介したマナーや目安は、あくまで一般的な考え方です。費用や宗教・地域の慣習、家族構成などによって最適な対応は変わりますので、正確な情報は公式サイトや公的なガイドラインもあわせてご確認いただき、最終的な判断は葬儀社や寺社などの専門家にご相談ください。そうすることで、あなた自身も「これで良かったんだ」と納得しやすくなると思います。
悲しみに向き合う時間の中で、あなたの弔電とプリザーブドフラワーが、ご遺族の心にそっと寄り添う一つの支えとなることを願っています。この記事が、その一歩を踏み出すお手伝いになればうれしいです。