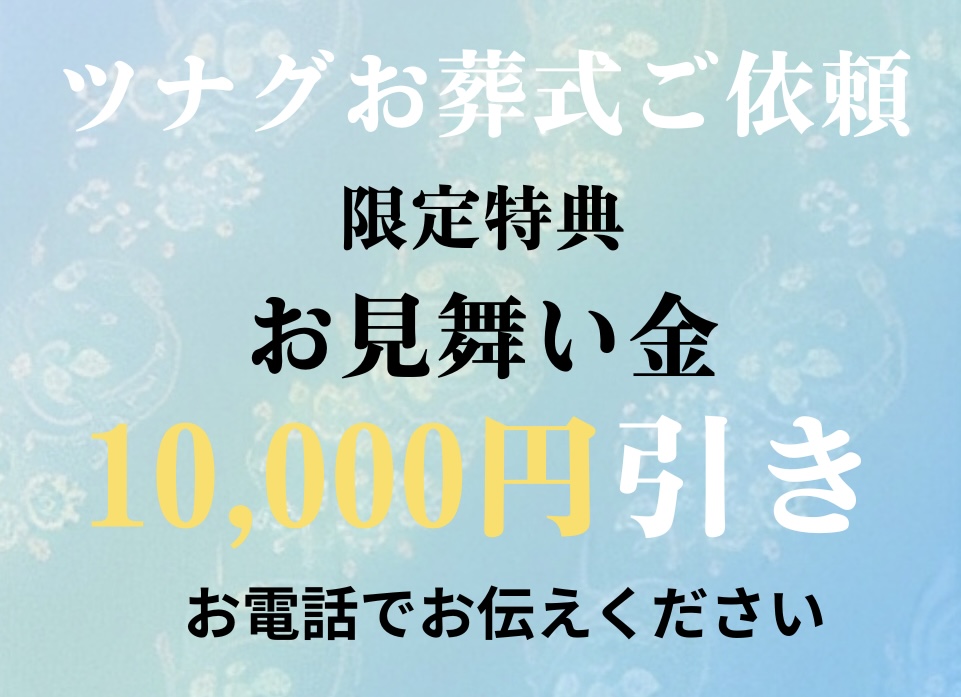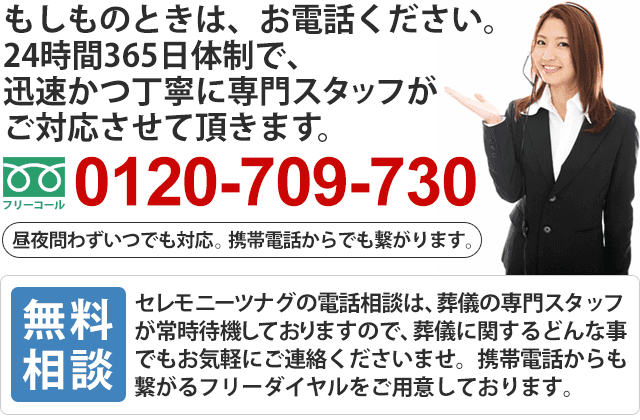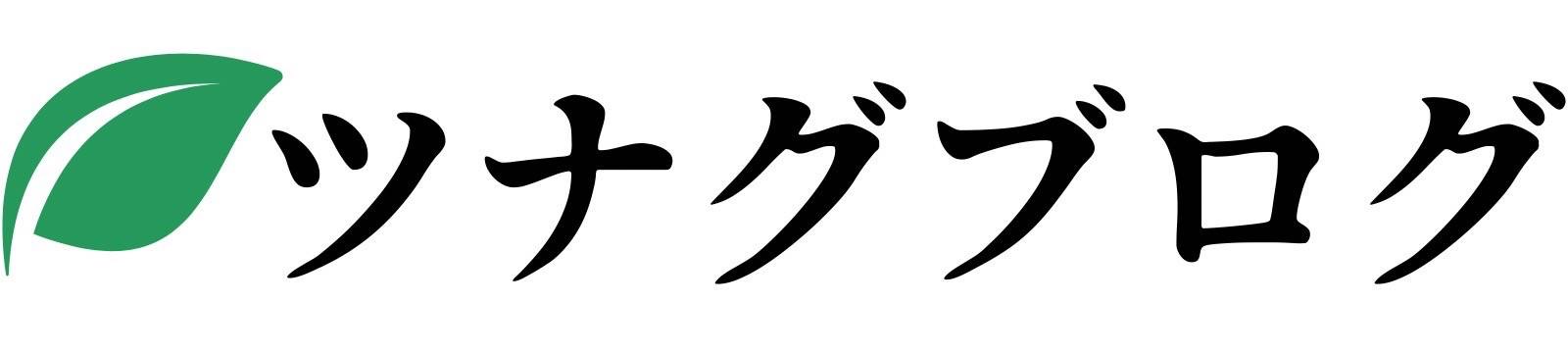24時間365日 無料で相談する
法事に数珠はいらない?忘れた時等の完全マナーガイド

こんにちは。西宮市で家族葬や法事をお手伝いしているセレモニーツナグです。
法事の案内を受け取ってから「法事で数珠はいらないのでは?」「そもそも法事に数珠は必要なのか」「法事で数珠を忘れたらどうしよう」「法事で数珠を持ってないのはマナー違反?」といった不安を抱えてご相談いただくことがとても多くあります。
実際に現場では、法事の直前に「数珠を忘れた」「数珠の代用になるものはある?」「家族葬なら数珠はいらない?」「直葬や火葬式だと数珠はいらないと聞いたけれど本当?」「子供にも数珠は必要?」と、数珠まわりの疑問が一気に押し寄せがちです。
さらに最近は、インターネットで法事の情報を調べる中で「数珠がないとマナー違反」「いや、気持ちがあれば数珠はいらない」と真逆の情報に触れ、「結局どちらを信じれば良いのか分からない」という声も耳にします。中には、急いで100円ショップで数珠を買うべきか迷っている方や、ブレスレットを数珠代わりにしても良いのか気にされている方もいます。
初めての法事だったり、親族が少ない家だったりすると、身近に「これで合っているよ」と教えてくれる人がいないことも多いですよね。そうなると、「知らないまま失礼なことをしてしまうのでは?」と余計に不安になりやすいかなと思います。
この記事では、セレモニーツナグとしてこれまで数多くの法事をお手伝いしてきた経験をもとに、「法事で数珠はいらないのか」「忘れた時にどう動けば良いのか」「家族葬・直葬・子供の参列など状況別の考え方」まで、できるだけ分かりやすく整理してお伝えします。
読み終えるころには、ご自身の状況で数珠をどう準備し、もし手元になくてもどんな振る舞いを心がければよいか、落ち着いて判断できるはずです。「これなら当日を迎えても大丈夫そうだ」と少しでも気持ちが軽くなれば嬉しいです。
- 法事で数珠が必要とされる理由と基本マナーが分かる
- 数珠を忘れた、持っていない場合の具体的な対処法が分かる
- 家族葬や直葬、子供の参列時など状況別の考え方が分かる
- 今後のためにどのような数珠を準備しておくと安心かが分かる
法事の数珠はいらないのか?
まずは「法事に数珠はいらないのか」という一番気になる疑問から整理していきます。ここでは、数珠の意味や歴史的な背景、法事で数珠が必要とされる理由、そして「数珠を忘れた・持っていない」時の基本的な考え方をお伝えします。そもそも日本では仏教系の宗教行事が多く、仏式のお葬式や法事が一般的ですよね。その中で数珠がどんな位置づけなのかを知っておくと、「持つべきかどうか」のモヤモヤがかなり整理されてきます。
法事で数珠を忘れた時の対応

法事当日に会場へ向かう電車の中や、玄関を出た直後に「数珠を忘れた」と気づくことは、決して珍しいことではありません。現場でも、開式前の控室でそのことに気づき、困った表情で相談される方を何度も見てきました。「もう間に合わない…どうしよう」と焦ってしまうお気持ち、すごくよく分かります。
そんなときに一番大切なのは、まず深呼吸をして落ち着くことです。仏式の法事では数珠を持参するのが基本的なマナーですが、数珠がないからといって法事に参列できないわけではありません。私がご案内するときも、まずは「数珠がなくても参列できますので安心してください」とお伝えしています。ここで慌てて行動してしまうと、遅刻してしまったり、かえってご遺族に心配をかけてしまうこともあるので注意したいところです。
当日に気づいたときの優先順位
対応の優先順位としては、次のように考えると迷いにくくなりますよ。
数珠を忘れたときの基本的な考え方
- 可能であれば、開式前に数珠を用意する
- 用意が難しければ、数珠なしで静かに参列する
- 言い訳よりも、所作と態度を丁寧にすることを優先する
時間に余裕があれば、会場へ向かう途中で数珠を購入するという選択肢もあります。大きな仏具店だけでなく、ショッピングセンターやホームセンター、紳士服店、場合によっては100円ショップでも略式の数珠が手に入ることがあります。出発前にスマホで「数珠 売ってる 〇〇駅」のように検索してみると、意外と近くに取り扱い店が出てくることも多いですよ。
会場に着いてからできること
一方、開式まで時間がない、土地勘がないといった状況で無理に買いに走ると、かえって遅刻してしまうこともあります。その場合は、会場に到着した際にスタッフに「数珠を忘れてしまったのですが」と相談してみてください。葬儀会館やお寺によっては、数珠の販売や貸し出しを行っていることもあります。
会場到着後のおすすめ行動フロー
| 到着後すぐ | 受付やスタッフに声をかけて、数珠を忘れた旨を簡潔に伝える |
|---|---|
| 数珠が購入・貸出可能な場合 | 案内に従って購入またはお借りし、開式までに手元に用意する |
| 数珠の用意が難しい場合 | 「今回は数珠なしで、できる限り丁寧に合掌する」と気持ちを切り替える |
それでも手元に数珠が用意できない場合、無理に誰かから借りようとする必要はありません。次の見出しでも詳しく触れますが、数珠は一人一つが基本とされる仏具で、貸し借りを避けたほうが良いとされています。そうした意味でも、借りるより「数珠なしで、できる限り丁寧に合掌する」ことを優先した方が良いと私は考えています。
焼香の際は、左右の手をきちんと合わせ、背筋を伸ばして一礼し、静かに香をくべる。この基本を守れば、数珠の有無よりも「礼を尽くしている姿」がしっかり伝わります。「忘れてしまった自分」を責めすぎず、「今できる最善のマナーを意識する」という切り替えが大事かなと思います。
法事で数珠を持ってない人へ

そもそも「数珠を持っていない」「これまで必要性を感じたことがなかった」という方も多いものです。特に初めて法事に呼ばれた若い方や、普段から仏事と縁が薄い方は、「この機会に数珠を買うべきか、それとも今回はなしで参列して良いのか」と迷われますよね。
私自身、事前相談で一番よく聞かれるのがこの質問です。「一回きりのために買うのもな…」「でも持ってないと怒られたりする?」と、気持ちが行ったり来たりしてしまうところかなと思います。
今回だけ乗り切る?それとも今後も見据える?
私は、次の二つの視点から考えると分かりやすいと思っています。
数珠を持っていない人が考えたい二つの視点
- 今回の法事に失礼がないかどうか
- 今後の葬儀・法事でも安心して参列できるかどうか
まず、今回の法事について。仏式の法事であれば、数珠を持参するのが好ましいのは事実です。ご親族の中には「大人なら数珠の一つくらいは持っていて当然」と考える世代の方もいらっしゃいます。その意味では、余裕があれば用意しておいた方が、周囲から見ても安心感があります。
ただ、現場の感覚として「数珠を持っていないから非常識」とまで感じる方は、以前より明らかに減ってきています。特に若い世代や友人知人の立場であれば、「初めての法事なら仕方がないよね」と受け止めてくださることがほとんどです。大切なのは、服装や言葉遣い、焼香の所作など、他の部分で丁寧さを心がけることです。
一つ持っておくとラクになる理由
もう一つの視点は、「今後の備え」として数珠を持っておくかどうかです。葬儀や法事は、ある日突然やってきます。そのたびに「法事で数珠はいらないだろうか」と悩むより、略式の数珠を一つ用意しておけば、気持ちに余裕を持って参列できます。
価格帯は素材によってさまざまですが、一般的な略式数珠なら数千円程度から、簡易なものなら千円前後から見つかります。あくまで目安ですが、頻繁に買い替えるものではありませんので、無理のない範囲で「これなら長く大切にできそう」と思えるものを一つ選んでおくと良いでしょう。
数珠を一つ持っておけば、突然の訃報があったときも「喪服・数珠・香典袋」をサッと用意するだけで出発できます。バタバタと買い物に走らなくて済むので、結果的に故人のことを考える時間も増やせるかなと思います。
なお、法事以外のマナー全般が気になる方は、同じツナグブログ内のお通夜とお葬式のマナー解説記事もあわせて読んでみると、全体のイメージがつかみやすいですよ。
まとめると、「今回、どうしても用意が難しければ数珠なしで参列しても大丈夫。ただし、今後のことを考えると、一つ用意しておくと安心」というのが、現場で多くの方を見てきた私の実感です。「これから先も家族や親族の法事が続きそうだな」という場合は、どこかのタイミングで一度数珠を用意しておくと、気持ちがぐっとラクになりますよ。
法事に数珠は必要なマナーなのか

では、マナーとして「法事に数珠は必要か」と問われたとき、どのように考えればよいでしょうか。結論から言えば、仏式の法事では「数珠を持っていくのが望ましい」というのが基本です。「絶対これがないとダメ」という厳しい決まりではないものの、「持っていれば安心できるアイテム」として位置づけておくとイメージしやすいかなと思います。
数珠が大切にされてきた背景
数珠は、もともと念仏やお経を唱える回数を数えるための道具として生まれました。やがて「煩悩の数」とされる百八の珠が並ぶ形が整い、仏様やご先祖様に向き合うときに心を整える役割を担うようになりました。現在の日本では、参列者が実際に珠を繰る場面は少ないですが、それでも「仏さまへ手を合わせる姿を整える仏具」として大切に扱われています。
日本全体で見ても、仏教系の宗教行事は今も広く行われていて、葬儀や法事の多くは仏式です。文化庁が公表している宗教統計でも、仏教系の信者数は依然として多く、日本の暮らしの中で仏教行事が根付いていることが分かります。(出典:文化庁「宗教年鑑」)
法事の席では、読経の間や焼香のときに、手に数珠をかけて合掌する姿がごく自然な光景として定着しています。こうした背景から、法事の案内状にも明記されていなくても、「喪服・香典・数珠」の三点セットを持参するのが標準的なマナーと考えられています。
「持っていない=即マナー違反」ではない
とはいえ、数珠がないことが直ちに重大なマナー違反かと言われると、そこまで厳格ではありません。現代では宗教観も多様になり、仏教に馴染みの薄い方が増えています。私自身もご遺族から「若い人なら忘れることもあるよ」と穏やかに受け止めていただく場面を何度も見てきました。
数珠は「必ず持っていないと参列できない」ものではなく、「あることでより丁寧な気持ちを表せる」ものと捉えると、バランスが取りやすくなります。
大切なのは、「数珠があるかないか」そのものよりも、「数珠をどう扱い、どのような気持ちで手を合わせるか」です。数珠をポケットに入れっぱなしにしたり、振り回すように扱ったりすれば、たとえ持っていてもマナー違反です。一方、数珠がなくても、静かに背筋を伸ばし、心を込めて合掌していれば、ご遺族にはその誠意がきちんと伝わります。
また、宗派や地域によって「数珠の扱い方」や「必須と考える度合い」には差があります。関西と関東でも少し空気感が違ったりしますし、菩提寺の方針によっても変わることがあります。正確な作法や判断に迷ったときは、法事をお願いしているお寺や葬儀社に確認するのが一番です。
このページでお伝えしている内容はあくまで一般的な考え方です。正確な情報は公式サイトや寺院の案内をご確認いただき、最終的な判断は専門家にご相談ください。「これが100%の正解」というより、「失礼にならないための安全ライン」として受け止めていただければと思います。
法事の数珠を代用でしのぐ
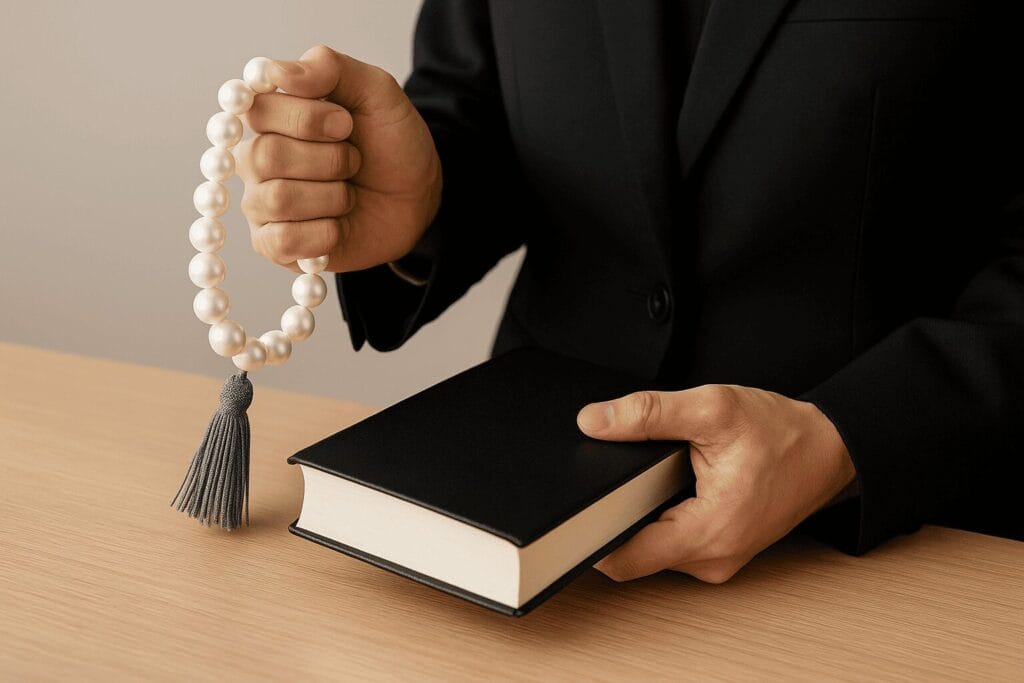
「数珠をどうしても用意できない」「買うべきか迷っているけれど、今回は間に合いそうにない」という場面では、完全な代用品ではないものの、手元を落ち着かせる工夫でしのぐこともできます。ここは特に気になるところかなと思います。
ハンカチや袱紗をそっと添える
まず、よく聞かれるのが「黒いハンカチで代用できますか?」という質問です。ハンカチ自体が数珠の代わりになるわけではありませんが、手に小さく畳んだハンカチを軽く添えて合掌すると、「何も持たずにそわそわしてしまう」感覚が和らぎます。他の参列者から目立つこともほとんどありません。
また、香典を包んだ袱紗を持っている場合には、合掌時に袱紗の端を軽く持つ方もいらっしゃいます。これも正式な代用とは言えませんが、「手の置き場に困る」「緊張して手先だけが妙に動いてしまう」といった状態を防ぐには有効です。指先の行き場があるだけで、ずいぶん気持ちがラクになりますよ。
「代用に見せる」ことを目的にしない
大切なのは、「数珠がないことを隠そう」とするのではなく、「今あるもので、できるだけ落ち着いた所作にする」という発想です。あくまで数珠の代わりを演じるのではなく、自分の心を整えるための小さな工夫と考えていただくと良いと思います。
注意したいポイント
- ハンカチや袱紗を派手に振り回したり見せびらかしたりしない
- 派手な柄物やキャラクターものはできるだけ避ける
- 「これは数珠の代わりです」と周囲に宣言する必要はない
数珠が用意できなかったことを気にしすぎるあまり、周囲に弁明したくなる方もいらっしゃいますが、列の中で長々と言い訳をする方が、かえって場の空気を乱してしまいます。黙って静かに合掌していれば、ほとんどの方は数珠の有無に意識を向けていません。
最優先は「静かで丁寧な立ち振る舞い」
応急的な工夫としては、ハンカチや袱紗が役に立ってくれますが、何よりも大事なのは「静かで丁寧な立ち振る舞い」です。焼香のときに慌てて順番を間違えたり、スマホの通知音が鳴ってしまったりする方が、数珠よりずっと印象に残ってしまいます。
ですので、「今回は数珠がない分、他のマナーはより丁寧にしよう」と決めておくと良いかなと思います。例えば、早めに会場に着く、受付ではっきり挨拶をする、読経中は姿勢を正して静かに座る、などですね。
あくまで応急的な工夫ではありますが、「今回はこうしてしのいで、今後に備えて数珠を一つ用意しよう」と考えていただければ十分だと思います。次回からは数珠の心配が減るぶん、故人のことを落ち着いて思い出す時間に使ってもらえるはずです。
法事の数珠を100均で用意

最近は、数珠を準備する方法の一つとして「100円ショップで数珠を買う」という選択肢も珍しくなくなってきました。現場でも、簡易的な数珠を手にされている方を拝見することがありますし、「急いで100均で買ってきました」と打ち明けてくださる方もいます。
100均の数珠は失礼?
「100均の数珠では失礼にならないか?」と不安に感じる方も多いのですが、私の印象としては、見た目が落ち着いていて、きちんと仏具として扱っていれば、価格そのものを気にされる方はほとんどいません。法事の場で「その数珠はいくらだったの?」と聞く人はいませんし、遠目から見て素材のランクまでは分からないものです。
もちろん、本式の数珠と比べれば、素材や作りの面で違いはあります。ただ、急な法事や葬儀で「手ぶらのままよりは、簡易的でも数珠を持っていたい」と考えるのであれば、100円ショップの数珠を一時的な相棒として用意するのも一つの方法です。
選び方のポイント
100円ショップの数珠を選ぶときの目安
- 色味が黒・グレー・茶など、落ち着いたもの
- 房が派手すぎないもの
- ブレスレット風ではなく、数珠の形をしているもの
あくまで一般的な目安ですが、「パーティーアクセサリー」といった雰囲気が強いものは避けた方が無難です。一度手に取ってみて、「仏前で手を合わせる自分の姿」に違和感がないかどうかを基準に選んでみてください。
また、100均の数珠はどうしても糸が切れやすかったり、房がほつれやすかったりすることがあります。使用頻度が高くなりそうな場合は、「今回は100均でしのいで、後日ゆっくり専門店で選び直す」という考え方がいいかなと思います。
長い目で見れば、専用の一連を
長い目で見れば、ご自身の宗派や好みに合った数珠を専門店や仏具店で選ぶのが理想的です。珠の素材や房の色、サイズ感など、自分が「しっくりくる」と感じるものを選ぶと、手に取ったときの安心感がまったく違ってきます。
ただ、「今すぐ必要」という状況では、100円ショップの数珠が救いになることも確かです。必要に応じて上手に活用しつつ、落ち着いて選べるタイミングで、長く使える一連を用意しておくことをおすすめします。
なお、法事全体の費用感や直葬・家族葬など形式ごとの違いが気になる場合は、西宮市の相場をまとめた家族葬の費用とプラン解説ページも参考になると思います。数珠だけでなく、全体像を知っておくと判断しやすくなりますよ。
法事で数珠はいらない場合
ここからは、「法事によっては数珠がいらない場合もあるのか」という視点で、状況別に分けてお話しします。家族葬や直葬・火葬式、子供の参列、ブレスレットの扱いなど、「これってどうなんだろう?」とよく聞かれるテーマを整理していきます。「ここは絶対」「ここは少しゆるくても大丈夫」といった感覚をつかんでもらえると、不安がかなり減ると思います。
子供は法事で数珠はいらない?

小さなお子さんを法事に連れていくとき、「子供にも数珠を持たせるべきか」「なくても失礼にならないか」と悩まれる親御さんはとても多いです。現場でも、「まだうちの子には早いのでは」「落として壊してしまわないか心配」といった声を聞きます。親としては「マナーも教えてあげたい」「でも子供に負担はかけたくない」と、気持ちが揺れますよね。
年齢による目安
私の考えとしては、小学校低学年くらいまでのお子さんであれば、無理に数珠を持たせなくても大丈夫だと感じています。数珠はとても細かな作りのものも多く、子供にとってはどうしても「面白そうなもの」「引っ張ってみたいもの」に見えてしまいます。結果として、房を引きちぎってしまったり、床に落として玉が飛び散ってしまったりすることも珍しくありません。
そうしたトラブルを防ぐ意味でも、幼いお子さんについては「数珠なしで、親御さんと一緒に手を合わせる」スタイルで十分だと思います。周囲の大人も、子供が数珠を持っていないことを気にする方はほとんどいません。それよりも、席を立ち歩いたり大きな声を出したりしないよう、親子でできる範囲で工夫してあげる方が大切かなと思います。
中学生くらいから「一人前」扱いに
一方で、小学校高学年〜中学生くらいになると、数珠を丁寧に扱うこともできるようになってきます。この年代のお子さんには、「大人と同じように一人前の参列者として扱う」という意味で、本人専用の略式数珠を用意してあげるのも良いタイミングです。
最初は親御さんが持ち方を教えながら、「おじいちゃん、おばあちゃんの前ではこうやって手を合わせるんだよ」と一緒に練習してみてください。数珠を持つこと自体が、先祖を大切にする気持ちを伝える小さなきっかけになることも多いです。
お子さんに数珠を持たせるかどうかは、年齢だけでなく、日頃の様子や性格も含めて総合的に判断してあげてください。落ち着いて座っていられる子もいれば、じっとしているのがまだ難しい子もいます。迷ったときは、菩提寺や葬儀社などに相談して、一般的な目安を聞いてみると安心です。
いずれにしても、「子供が数珠を持っていないから失礼」という考え方はあまり一般的ではありません。大人がしっかりとマナーを守りつつ、「一緒に手を合わせてくれてありがとう」という気持ちで見守ってあげることが一番の供養になるかなと思います。
家族葬で数珠はいらない場合

「家族葬なら数珠はいらない」といったイメージをお持ちの方もいます。確かに家族葬は、一般の会葬者を招かず、身内だけでゆっくりお別れをするスタイルです。そのため、「厳しいマナーは気にしなくて良いのでは」と考えたくなるお気持ちもよく分かります。
家族葬でも仏式なら基本は同じ
結論としては、家族葬であっても、仏式で法要が行われるのであれば、基本的には数珠を持参した方が良いとお伝えしています。読経や焼香がある限り、儀式の内容そのものは一般葬と変わりません。
ただし、家族葬は「形式よりも、故人らしさや家族の思いを大切にしたい」という意図で選ばれることが多いお葬式の形でもあります。実際、ご遺族から「身内だけだから、多少のことは気にしないで」と言われる場面もあります。そうした場合には、数珠がないことが理由で責められることはほとんどありません。
関係性や立場による「優先度」の違い
家族葬で数珠に悩んだときの考え方
- 仏式で読経・焼香があるなら、できれば数珠を持参する
- どうしても用意できなければ、身内同士で事前に共有しておく
- 「家族葬だからこそ、心を込めて手を合わせる」ことを最優先にする
特に、喪主や近い親族の立場で参列する場合、数珠の有無は周囲から見られやすいポイントでもあります。ご親族同士で写真を撮ることも増えているので、「記録に残る」という意味でも、できるだけ用意しておいた方が安心です。
一方で、少し離れた親族や親しい知人として家族葬に招かれた場合、数珠がなくても「そこまで気にしなくていいですよ」と言われるケースもあります。迷ったときは、招いてくれた側にさりげなく確認しておくのも一つの方法です。
家族葬そのものの考え方やマナーについては、ツナグブログ内の家族葬での振る舞い方を解説した記事も参考になると思います。香典や参列範囲など、数珠以外のポイントもセットで押さえておくと安心ですよ。
直葬や火葬式で数珠いらない?

最近増えているのが、通夜や告別式を行わず、火葬場でのお別れを中心に行う直葬や、簡素な火葬式です。この場合、「読経も短いし、数珠はいらないのでは?」と考える方も多くいらっしゃいます。
直葬と火葬式、それぞれのイメージ
直葬・火葬式と一口に言っても、実際の進行はご家族の希望によってさまざまです。お坊さんを招いて火葬炉前でしっかり読経を行うケースもあれば、合掌だけで静かに見送るケースもあります。
大まかに言うと、直葬は「読経などの儀式を基本的に行わない、火葬のみ」の形、火葬式は「火葬を中心にしつつ、短い読経やお別れのセレモニーを行う」形というイメージです。宗教者を招くかどうかで、雰囲気もかなり変わってきます。
数珠の優先度は「読経や焼香があるか」で考える
「仏式として読経や焼香、合掌の時間があるなら、直葬や火葬式でも数珠はあった方が望ましい」
とはいえ、直葬は時間的な制約が大きく、「連絡が来てそのまま駆けつけた」という状況になりやすい形でもあります。そうした場合、数珠どころか喪服も間に合わないことが珍しくありません。そのようなときは、無理に準備を優先するよりも、「来てくださったこと自体が何よりの供養」とご遺族が考えていることが多いと感じています。
直葬や火葬式に呼ばれたときは、事前に案内状や連絡事項をよく読み、「どの程度の形式で行うのか」を確認しておくと安心です。不明な点があれば、葬儀社や喪主に相談し、数珠を含めた持ち物について尋ねてみてください。特に直葬・火葬式に関しては、ツナグブログ内の直葬でお坊さんを呼ばない場合の解説記事も、全体像をつかむのに役立つと思います。
このページでお伝えしている内容はあくまで一般的な目安です。実際の進行やマナーは、地域や葬儀社によって違いがありますので、正確な情報は葬儀を担当している葬儀社や寺院の公式な案内をご確認いただき、最終的な判断は専門家にご相談ください。
数珠代用ブレスレットはNG

最近はパワーストーンや天然石のブレスレットを身につけている方も多く、「これを数珠代わりにしても良いですか?」と質問されることがあります。見た目も似ているものが多いので、「これで代用できそう」と思ってしまいますよね。
アクセサリーと仏具の違い
結論から言うと、ブレスレットをそのまま数珠の代わりとして使うのは避けた方が良いと考えています。見た目が似ていても、ブレスレットはあくまでアクセサリーであり、法事の場で使う仏具として作られたものではありません。
ブレスレットを合掌時に目立つ形で見せてしまうと、「おしゃれのアクセサリーを見せている」と受け取られる可能性もあります。特に年配の方や、宗教的な意味合いを大切にされる方にとっては、違和感のある光景に映ってしまうかもしれません。
なぜNGとされやすいのか
ブレスレットを数珠代わりにしない方が良い理由
- 仏具としての形や作りになっていないため
- アクセサリー感が強く、場の雰囲気にそぐわないことがあるため
- 「マナーよりファッションを優先している」と見られる恐れがあるため
「誰もそこまで見ていないのでは?」と思うかもしれませんが、法事のような静かな場では、案外ちょっとした装いの違いが目に入りやすいものです。特に近しい親族の立場であれば、「あのブレスレットはどうなんだろう」と感じる方がいてもおかしくありません。
腕輪念珠という選択肢もある
もし「腕につけられるタイプの方が使いやすい」という場合は、仏具店などで売られている腕輪念珠を選ぶと良いですよ。これはブレスレットに近い形ですが、「仏具として作られた数珠」なので、法事の場でも安心して使えます。
とはいえ、腕輪念珠であっても、法事のときには手に持って合掌した方が気持ちが入りやすいかなと思います。いざというときに備えて、通常の略式数珠と腕輪念珠を使い分ける、という形もありです。
もし腕にブレスレットをつけたまま法事に参列する場合は、会場に入る前に外しておくことをおすすめします。そのうえで、数珠を持っていれば数珠を手に、持っていなければ素手で静かに合掌するのが、もっとも自然で丁寧な形です。数珠としても使える腕輪念珠というものもありますが、これも「仏具として作られたもの」であることがポイントです。単なるパワーストーンブレスレットとの違いを意識して選ぶようにしてください。
法事で数珠はいらないか結論
最後に、「法事で数珠はいらないのか」というテーマについて、セレモニーツナグとしての結論をまとめます。ここまで読んでくださったあなたなら、もうかなりイメージがついてきていると思います。
基本スタンス:あった方が安心、なくても工夫はできる
まず、仏式の法事において、数珠は「基本的には持っていくのが望ましい」仏具です。読経や焼香の場面で数珠を手にして合掌する姿は、故人と真剣に向き合う気持ちの表れでもあります。今後も法事や葬儀に参列する可能性があるなら、ご自身用の略式数珠を一つ用意しておくことを、私は強くおすすめします。
一方で、数珠を忘れてしまったり、まだ持っていなかったりすることを、過度に恐れる必要はありません。家族葬や直葬、子供の参列など、状況によっては数珠がなくても責められないケースも多く、何よりも大切なのは「故人を想い、静かに心を込めて手を合わせること」です。
今日からできる「3つの準備」
法事の数珠で迷わないための三つの準備
- 略式数珠を一つ用意して、喪服と一緒に保管しておく
- 法事に呼ばれたら、案内状や寺院からの連絡をしっかり読む
- 不安なことは、早めに葬儀社やお寺に相談して確認しておく
数珠を用意できなかったときは、無理に借りたり代用品で取り繕ったりするよりも、焼香の所作や立ち振る舞いを丁寧に整えることを優先してください。姿勢、挨拶、合掌の一つ一つに気持ちがこもっていれば、それだけで立派な供養になります。
この記事でお伝えした内容は、あくまで一般的な目安や、セレモニーツナグとしての現場での経験をもとにした考え方です。実際の作法や必要な持ち物は、宗派や地域、お寺ごとの考え方によって異なる場合があります。正確な情報は公式サイトや寺院・葬儀社からの案内をご確認いただき、最終的な判断は専門家にご相談ください。
法事の数珠についての不安が、この記事をきっかけに少しでも軽くなり、「これなら大丈夫」と落ち着いて当日を迎えていただけたら嬉しく思います。分からないことや心配ごとがあれば、どうか一人で抱え込まず、身近な専門家に気軽に相談してくださいね。あなたとご家族の大切な時間が、心穏やかに過ごせますように。