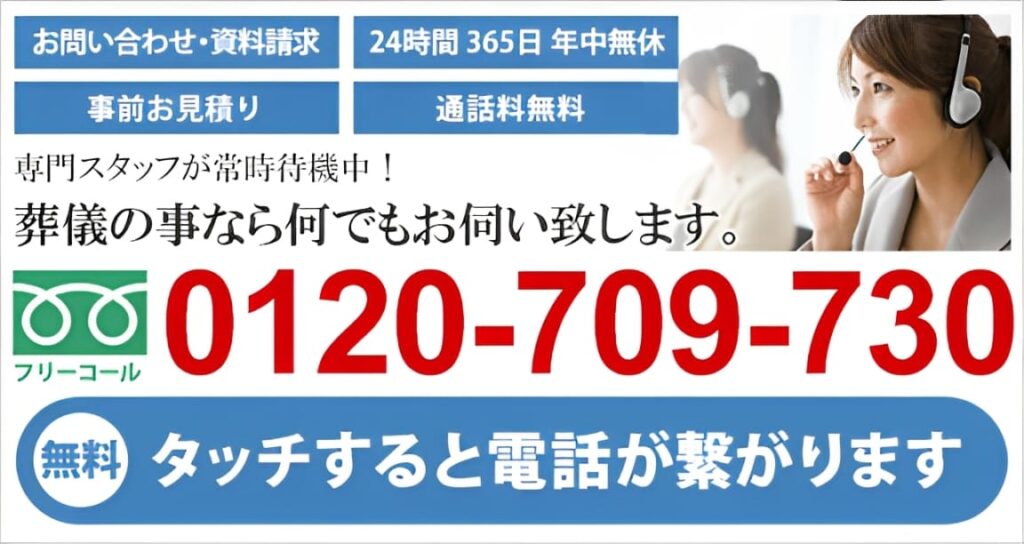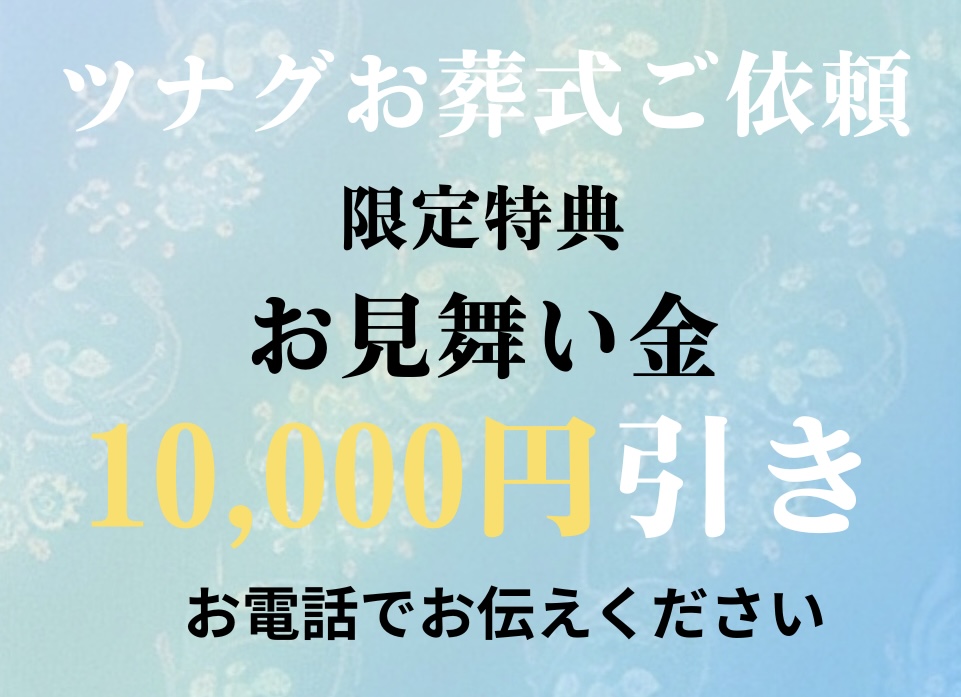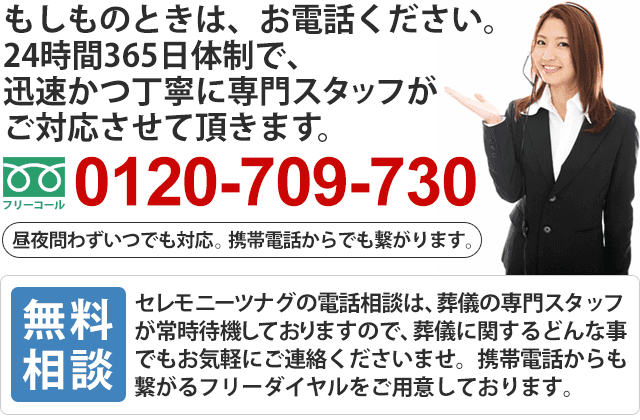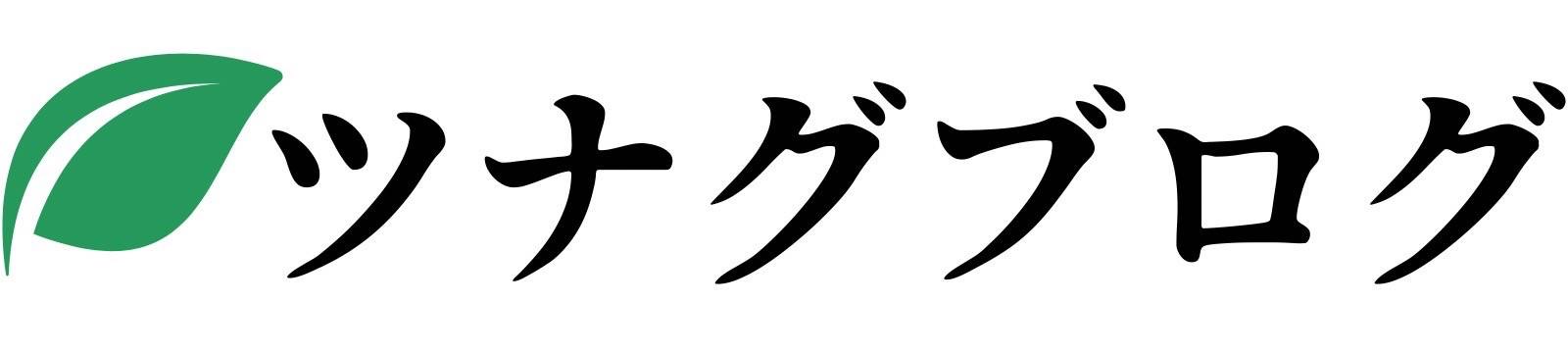24時間365日 無料で相談する
亡くなった人が成仏するには供養とお経が本当に必要なのか

誰もが一度は耳にしたことがある「成仏」という言葉。しかし、その意味や背景について正確に理解している人は意外に少ないかもしれません。「亡くなった人が成仏するには」と検索したあなたも、供養の方法や死後の世界について悩みや疑問を抱えているのではないでしょうか。
この記事では、「成仏とは簡単にどういうことか」「人は死後何日で成仏しますか?」といった基本的な疑問から、「お経をあげないと成仏できないのか」「戒名がないと成仏できないの?」といった現代的な不安にまで丁寧にお答えしていきます。また、「即身成仏とはわかりやすく何か」「成仏できないと虫になるというのは本当か」「成仏できない現象とは何か」といった少し踏み込んだ話題も、仏教的な観点からやさしく解説していきます。
さらに近年関心の高まる「樹木葬は成仏できない?」という疑問についても、現代供養の在り方とあわせてご紹介します。正しい知識を持ち、故人を想う気持ちを形にすることは、残された人にとっても心の整理につながります。この記事を通じて、成仏にまつわる不安を少しでも軽くし、穏やかな気持ちで故人と向き合える手助けとなれば幸いです。
- 成仏とは何を意味するのか基本から理解できる
- 成仏のために必要な供養や儀式の内容がわかる
- 成仏を妨げる原因や現れる現象について知ることができる
- 戒名やお経、樹木葬などに関する不安が解消できる
亡くなった人が成仏するには供養が大切
- 即身成仏とはわかりやすく解説
- 樹木葬は成仏できない?という不安
- 成仏を妨げる執着や未練とは何か
- 成仏を願う供養方法と現代の考え方
- 成仏とは簡単にどういうことか解説
- 人は死後何日で成仏するのか?
- 四十九日法要の意味と必要性とは
- お経をあげないと成仏できないのか
- 戒名がないと成仏できないの?
- 成仏できない現象とその背景
- 成仏できないと虫になるは本当か?
- 成仏できないと霊になる理由とは
- 亡くなった人が成仏するには供養が大切
- 亡くなった人が成仏するには正しい理解が必要
- 成仏とは簡単にどういうことか解説
成仏とは簡単にどういうことか解説

成仏とは、仏教における最終的な目的であり、「仏になること」を意味します。より平たく言えば、迷いや苦しみから解放されて安らかな境地に至ることを指します。多くの人が「亡くなった人が仏になること」と理解していますが、実際にはそれだけではありません。
仏教における「成仏」とは、煩悩や執着から解き放たれ、悟りの境地に達することを意味します。煩悩とは、人間が生まれながらに持つ欲望、怒り、嫉妬、不安などの感情のことです。これらの感情に振り回されず、心穏やかに真理を受け入れられる状態になることが「仏になる=成仏する」ことなのです。
とはいえ、実際に生きているうちに煩悩を完全に捨て去るのは非常に難しいとされています。そのため、現代では「亡くなった人が安らかにあの世に旅立てるよう祈ること」を成仏という言葉で表現することが一般的です。
例えば、葬儀や法要などで「どうか成仏してください」と手を合わせるのは、その人がこの世への未練を断ち切り、安らかに過ごしてほしいという願いを込めたものです。仏教の教義に厳密に従えば、成仏は生きている間の修行によってのみ到達可能な境地ですが、日常会話の中では「死後、迷わず安らかに過ごす」意味合いで使われています。
このように、成仏という言葉には本来の仏教的な意味と、日常的な慣用的な意味があり、それぞれの場面によって解釈が異なります。いずれにしても、心が安らかであることが成仏の共通したイメージといえるでしょう。
人は死後何日で成仏するのか?
仏教の考え方に基づくと、人は亡くなってから49日目に成仏するとされています。この49日間は「中陰(ちゅういん)」と呼ばれる期間であり、亡くなった人の魂があの世へ旅立つための準備期間だと考えられています。
この期間中、亡くなった人は7日ごとに「生前の行いに対する審判」を受けるとされており、合計7回、つまり49日間かけて魂の行き先が決まるというのが仏教の教義に基づく伝統的な考え方です。このため、葬儀の後には「初七日」から「七七日(四十九日)」まで法要を行い、供養を重ねていきます。
例えば、四十九日法要では僧侶の読経や焼香を通じて、故人が無事に極楽浄土へ向かえるように祈ります。この時点で「忌明け」とされ、多くの家庭ではこの日をもって喪に服す期間が終了し、日常生活に戻る準備を始めます。
一方で、現代では宗派によって考え方に違いがあり、必ずしも49日を成仏のタイミングとしない場合もあります。また、個々の遺族の考え方によっても異なることがあります。供養が心から行われることが何より大切であり、日数や形式よりも故人への思いを込めた祈りが重要視されるケースも増えています。
さらに、科学的な根拠はないものの「魂は四十九日であの世へ旅立つ」という考え方は、多くの人にとって心の区切りとなる目安でもあります。そうした意味で、四十九日法要は形式だけでなく、遺された家族が気持ちの整理をつける大切な節目ともいえるでしょう。このように、人は死後49日を経て成仏するとするのが仏教の一般的な見解ですが、重要なのはその期間中にいかに心を込めて故人を偲び、供養するかという点にあります。
四十九日法要の意味と必要性とは?

四十九日法要は、故人が亡くなってから49日目に行う仏教の重要な儀式です。この法要は単なる形式ではなく、故人の魂が安らかに旅立てるよう願いを込めた供養の一環として位置づけられています。
古くから仏教では、亡くなった人の魂はすぐに来世へ向かうのではなく、「中陰(ちゅういん)」と呼ばれる期間を49日間かけてさまよい、その間に7日ごとに審判を受けると考えられてきました。そして49日目には、次に生まれ変わる世界が定まり、魂が最終的な安住の地へ向かうとされているのです。つまり、この四十九日が一つの区切りであり、成仏を祈る上で重要な日と考えられています。
このときに行われる法要は、ただの形式的な行事ではありません。親族や知人が集まり、読経や焼香、仏前への供え物を通して、故人に対する感謝や祈りを捧げる機会になります。それにより、遺された人々の心にも整理がつきやすくなり、喪失の悲しみから少しずつ立ち直るための精神的な支えにもなるのです。
また、現代においては葬儀を簡略化する傾向が増えているものの、四十九日法要だけはしっかりと行いたいという人が少なくありません。それは、故人の冥福を祈るだけでなく、自分自身が納得して日常生活に戻るための「けじめ」として機能しているからです。
ただし、必ずしも豪華な準備や大人数での開催が必要なわけではありません。大切なのは、心を込めて供養することです。小規模でも丁寧に行えば、故人の魂はしっかりと受け取ってくれるでしょう。
このように、四十九日法要は仏教の教義に基づいた意味のある儀式であり、故人と遺族の双方にとって必要な節目といえます。現代の生活スタイルに合わせつつも、その本質を理解し、丁寧に向き合うことが望まれます。

お経をあげないと成仏できないのか

多くの方が「お経をあげなければ故人は成仏できないのでは?」と不安に思うかもしれません。しかし、実際のところ、仏教の教えには「お経が絶対条件」と明言されているわけではありません。
お経は、本来、仏の教えを言葉にして伝えるものであり、それを読むことで故人の魂に仏の真理を届け、迷いから解放しようとする意味合いがあります。そのため、僧侶によって読経が行われる葬儀や法要は、故人を安らかに導くための儀式として広く行われているのです。
ただし、宗派や地域の慣習によっては、お経をあげなくても成仏は可能であるという考え方も存在します。特に現代では、家族葬や直葬といった簡素な形式を選ぶ人も多く、「お経なし=成仏できない」と決めつけるのは適切とは言えません。
また、供養の本質は形式ではなく「心」にあります。たとえお経をあげられなくても、故人を想い、感謝や祈りの気持ちを込めて供養することが何よりも大切です。実際に、お経を自分で読むことに挑戦する人もいれば、仏壇の前で静かに手を合わせるだけの人もいます。そのどれもが、心を込めた供養の一つといえるでしょう。
一方で、「お経をあげないと成仏できない」と強く信じている親族がいる場合は、無用なトラブルを避けるためにも、僧侶に依頼することを検討したほうが安心です。家族内の考え方に違いがある場合は、事前に丁寧に話し合い、故人の意向と遺族の気持ちをすり合わせることが望まれます。このように考えると、お経は「成仏のための絶対条件」ではなく、「成仏を願う気持ちを表す一つの手段」と捉えるのが自然です。状況や考え方に応じて柔軟に対応しながら、故人を想う心を大切にすることが本当の供養につながるのです。

戒名がないと成仏できないの?

まず結論から言えば、戒名がなくても成仏は可能です。仏教の本来の教えでは、戒名の有無が成仏できるかどうかを決めるものではありません。しかし、戒名には宗教的・社会的に大きな役割があるため、「あったほうが望ましい」とされる場面も存在します。
戒名とは、仏門に入った証として授けられる名前であり、亡くなった方が仏の弟子として極楽浄土へ向かうことを象徴するものです。特に日本では、葬儀や法要で戒名を位牌に刻んだり、墓誌に彫刻するのが一般的となっており、供養の中心的存在とされることが多いです。
しかし、このような習慣は主に日本独自のものであり、仏教発祥の地であるインドや他の仏教国では、戒名を付けるという習慣自体が存在しません。つまり、戒名そのものは、仏教の根本的な教えではなく、後世における文化や慣習として形成されたものです。
一方で、戒名がないことにより、親族や寺院との関係で摩擦が生じるケースもあります。例えば、寺院の墓地に納骨を希望する場合、戒名がなければ納骨を断られることもあります。また、仏式の葬儀を行う場合には、読経とセットで戒名が必要とされるため、僧侶との事前相談が欠かせません。
さらに、親族の中には「戒名がないと浮かばれない」と強く信じている方もいるかもしれません。このような場合は、故人の希望とともに遺族の気持ちにも配慮し、事前に丁寧な話し合いを行うことが大切です。
また、近年では「生前に戒名を決めておく」人や、「自分で戒名を作る」人も増えています。宗派や寺院によって柔軟な対応がなされるケースも多く、形式だけにとらわれない供養の形が広まりつつあります。
このように考えると、戒名は成仏の絶対条件ではありませんが、残された家族が安心して供養を行い、故人との別れに心の整理をつけるための「象徴」としての意味合いを持つといえます。信仰心や宗派、故人の希望に応じて、柔軟に考えていくことが現代的な在り方かもしれません。
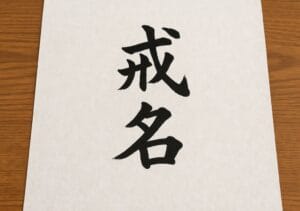
成仏できない現象とその背景

「成仏できない」とされる現象は、昔から人々の間で語られてきました。たとえば、事故現場や病室に現れる「地縛霊」、突然命を落とした人の魂が浮遊する「浮遊霊」など、いずれも成仏せずこの世にとどまっている存在として恐れられています。
これらの現象の背景には、「死者が心残りを抱えている」「自分が死んだことに気づいていない」「供養が十分に行われていない」といった要因があるとされます。つまり、**成仏できない理由の多くは、未練や混乱による“魂の迷い”**だとされているのです。
例えば、突然の事故や事件で命を落とした場合、本人が自分の死を受け入れられないままこの世に留まるケースがあると信じられています。そのため、死んだことに気づかず、日常を繰り返すような現象が「霊的な存在」として語られるのです。
また、強い未練を残してこの世を去った場合も、魂が現世に執着してしまうことがあるとされています。子どもを残して亡くなった親や、恨みや後悔を抱えて命を絶った人などは、心の整理がつかず、成仏できない霊として現れるという考え方が根強く残っています。
宗教的な観点から見ると、こうした霊魂は「六道輪廻」にとどまり続け、次の世界へ進めずにいる状態と考えられます。仏教では、すべての魂は因果の法則に基づいて次の世界に転生するとされていますが、煩悩や執着が強すぎる場合は、解脱できずに迷いの世界にとどまることになります。
では、こうした状態から魂を解き放つにはどうすればよいのでしょうか。一つの手段として、供養があります。丁寧にお経を唱え、思いを込めて焼香し、故人の気持ちに寄り添うことが、成仏への手助けになります。特に四十九日法要や年忌法要は、魂が迷いから解き放たれるための重要なタイミングとされています。
しかし、すべての霊的現象が迷える魂に由来するとは限らず、中には心理的な要因や偶然によって錯覚として感じられる場合もあります。ですので、必要以上に恐れることなく、「故人を想い、心から祈ること」が最も重要であり、それこそが成仏につながる行為と言えるでしょう。このように、成仏できない現象には様々な背景があり、単なる怪奇現象として片付けられない側面を持っています。心のこもった供養と故人への思いやりが、魂の安らぎにつながる第一歩です。
亡くなった人が成仏するには正しい理解が必要
成仏できないと虫になるは本当か?

「成仏できないと虫になる」という話を聞いたことがある方は少なくないでしょう。これは一見すると迷信のように思えるかもしれませんが、実は仏教における「輪廻転生」の考え方がもとになっている言い伝えです。
仏教では、人の魂は死後に「六道(ろくどう)」という六つの世界のいずれかに生まれ変わるとされています。この六道とは、天界・人間界・修羅界・畜生界・餓鬼界・地獄界のことで、その中でも動物や虫などの命に生まれ変わるのは「畜生道(ちくしょうどう)」にあたります。
つまり、仏教的な視点でいえば、「煩悩にとらわれていた人」や「悪業を多く積んだ人」は、人間としての生まれ変わりから外れ、畜生道へと転生する可能性があるとされるのです。虫もその一例であり、だからこそ「虫に生まれ変わる」という表現が生まれました。
このような話は特に家庭や地域に根付いた信仰として語られることが多く、例えば「虫が家に現れたときは、故人が何かを伝えに来たのかもしれない」と受け止める人もいます。虫を殺さないようにするとか、仏壇の周りに現れた虫を丁寧に扱うといった風習が、今でも一部には残っているのです。
ただし、現代においてはこの考え方をそのまま信じて恐れる必要はありません。むしろ、故人が何らかの形で身近に感じられることで、遺族が心の拠り所を見つける一つの手段として受け入れられていることもあります。
また、虫に限らず、身の回りに起こる小さな変化に対して「これは亡くなった人が伝えたいことかもしれない」と思うことで、自分の中にある故人への思いに気づくこともあるでしょう。そこから改めて供養の気持ちが芽生えるのであれば、それもまた大切な信仰のかたちです。
このように、「成仏できないと虫になる」という言い伝えには、仏教の教えと人々の生活感情が交差する背景があります。単なる迷信と切り捨てるのではなく、そこに込められた意味を知り、自分なりに向き合う姿勢が求められるのではないでしょうか。
成仏できないと霊になる理由とは
亡くなった人が成仏できずに霊になるという話は、昔からさまざまな形で語り継がれてきました。お盆や彼岸の時期になると、「帰ってきた霊を迎える」といった表現も耳にします。これらはすべて、成仏できなかった魂が現世に留まり続けるという考え方から来ています。
仏教における死後の世界では、魂は通常、四十九日の間にさまざまな審判を受けて次の世界へと旅立っていきます。しかし、その期間中に強い未練や怒り、悲しみ、執着といった感情を抱えていると、魂はその感情に縛られて「あの世」に行くことができず、この世にとどまり続けるとされています。
こうした魂の状態が「霊」と呼ばれるもので、いわゆる地縛霊や浮遊霊といった形で語られることが多いです。特に、事故死や自死、事件に巻き込まれたなど、突然の死を迎えた人の場合、「自分が死んだことを理解していない」「現世に対する感情が強く残っている」といった事情から、成仏できずに霊になると信じられています。
また、葬儀や法要が十分に行われなかった場合も、霊が落ち着かずに現世にとどまると考える人もいます。これは、供養によって魂の安寧を願うという仏教的な価値観から来ており、正しい手順を踏んで見送ることが故人の魂のために大切だとされる理由です。
さらに、成仏できなかった霊は、現世に悪影響を与えるとも言われています。家族間での不和や体調不良、原因不明の出来事などが霊の影響によるものとされるケースもありますが、これらは迷信や解釈の一部に過ぎず、すべてを霊の仕業とするのは早計です。
一方で、「霊になった」とされる存在も、しっかりと供養することで安心し、成仏へと導かれると考えられています。お経をあげたり、仏壇に手を合わせたり、故人を思い出して語りかけたりすることで、残された思念が解かれていくと信じる人も多いです。このように、成仏できないと霊になるという考えは、人々の死生観と深く結びついています。単なる怪談や怖い話としてではなく、故人への思いをどう形にして表すかという供養のあり方として、向き合っていくことが大切だといえるでしょう。
即身成仏とはわかりやすく解説
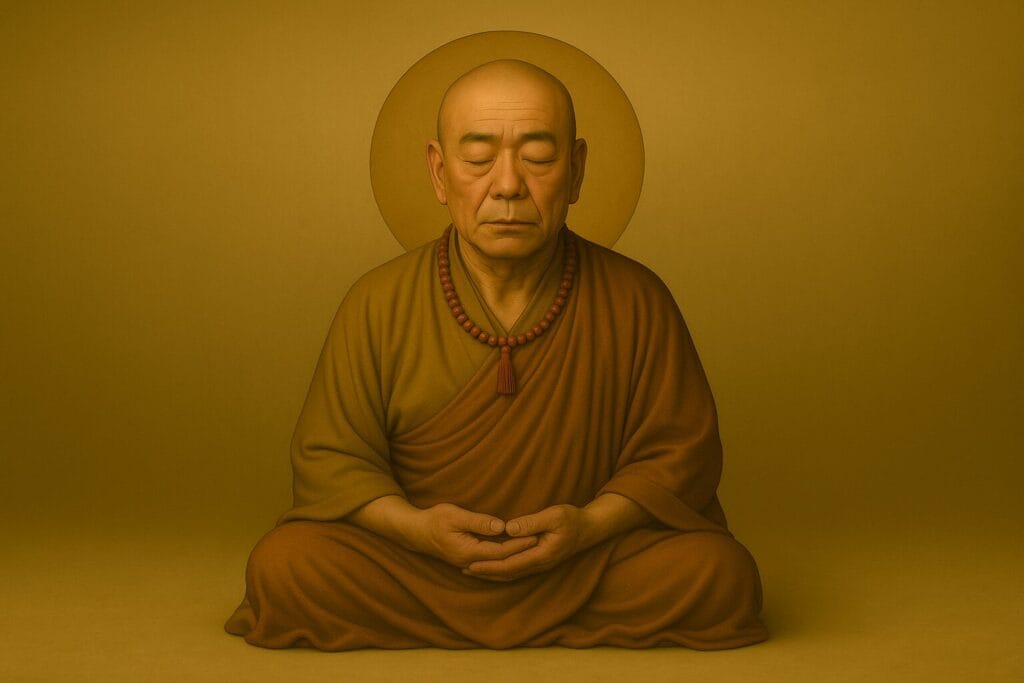
「即身成仏(そくしんじょうぶつ)」という言葉は、仏教に関する話題でときおり目にするものの、意味がわかりづらいと感じる方も多いかもしれません。これはとても奥深い教えですが、ここではできるだけやさしく、わかりやすく解説します。
即身成仏とは、生きたまま仏の境地に至ることを意味する言葉です。ふつう仏教では、修行を重ねたあとに亡くなってから成仏するという流れが語られますが、即身成仏では「この身のままで悟りに到達できる」と説かれます。つまり、生きている今この瞬間に仏の心を宿すことができるという考え方です。
この教えは、特に真言宗で重視されています。空海(弘法大師)が説いた密教の教えにおいて、人は本来、仏と一体であり、その仏性(ぶっしょう)はすでに内に備わっているという発想から生まれました。仏になるのに何千年もの修行や来世を待つ必要はなく、正しい修法を通じてこの身このままで仏と一体化できるのだというのが即身成仏の根本です。
ただし、この考えを誤解して「即身成仏=ミイラ化して仏になること」と受け取る人も少なくありません。確かに、実際に自らを土中で埋めて生きながら仏になる修行を行った僧侶も歴史上には存在しました。しかし、それは即身成仏の一つの象徴的な表現にすぎず、思想そのものではありません。
現代において即身成仏という考え方は、もっと日常的なレベルで解釈されることが多くなっています。たとえば、自分の行動や考え方が他人を癒したり、助けたりするものであれば、それも一つの「仏の行い」であり、「即身成仏的な生き方」と言えるのです。
このように、即身成仏とは単なる宗教的な理論ではなく、今を生きる私たちの在り方を問いかける教えでもあります。自分の内にある仏性に気づき、それを日々の中で活かしていく――そうした生き方を目指すことが、現代における即身成仏の意味と言えるでしょう。
樹木葬は成仏できない?という不安

「樹木葬にすると成仏できないのでは?」と心配される方は意外に多いものです。自然志向や費用面から注目されている樹木葬ですが、伝統的な墓石と異なるため、「ちゃんと供養されるのか」「故人が浮かばれないのでは」といった不安の声があがるのも無理はありません。
まず前提として、仏教における成仏とは、魂が安らかに迷わず次の世界へと旅立つことを意味します。そして、成仏のために最も重要とされるのは「供養の心」です。墓の形が石であろうと樹木であろうと、それ自体が魂の行方を左右するわけではありません。
実際、多くの寺院や霊園では、樹木葬にも読経や法要の儀式が取り入れられています。専用の供養塔や合同墓を設けて、定期的に僧侶が読経を行う形式も一般的になりつつあります。つまり、樹木葬でも正しく供養されていれば成仏できないという心配は必要ないのです。
一方で、家族の中に「墓石がないと落ち着かない」と感じる方がいる場合、供養の方法についてしっかり話し合っておくことが大切です。形の違いに対する不安があっても、心を込めた供養があれば、故人の魂はしっかりと受け取ってくれると考えられます。
また、樹木葬は自然に還るという発想に基づいており、仏教の「無常観」や「自然との調和」とも深く結びついています。そういった意味では、むしろ仏教的な価値観に合った埋葬方法とも言えるでしょう。
近年では、跡継ぎがいない人や子どもに負担をかけたくないと考える人が樹木葬を選ぶ傾向も強くなっています。合同供養や永代供養とセットで提供されることも多く、供養の継続性に関しても安心できる仕組みが整えられつつあります。このように、「樹木葬は成仏できない」という不安は、正確な知識に基づけば解消できるものです。大切なのは形式ではなく、故人を想う気持ちと、供養を絶やさない姿勢であることを忘れないようにしましょう。
成仏を妨げる執着や未練とは何か
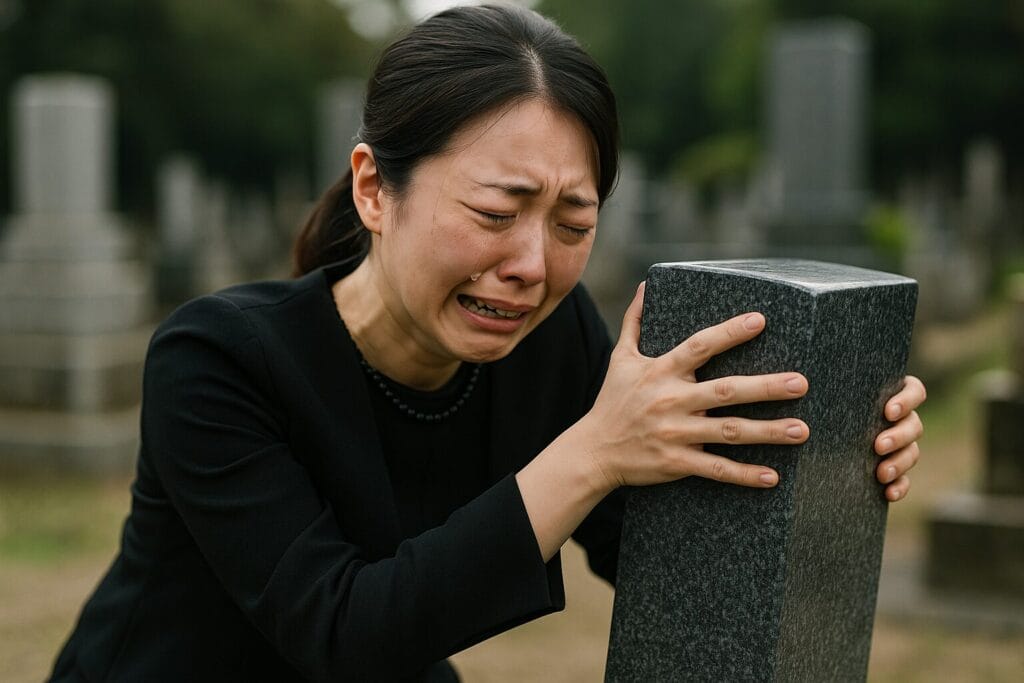
仏教の世界観において、「成仏できない原因の多くは“執着”や“未練”にある」とされています。つまり、亡くなった人がこの世に強い思いを残している場合、その魂が迷いの状態にとどまり、次の世界へ進むことができなくなるという考え方です。
執着とは、物や人、感情などに対して強くこだわる気持ちのことを指します。亡くなる直前まで何かに強く執着していた場合、たとえば「家族を残して逝くことへの心残り」「人生でやり残したことへの無念」「財産や地位に対する未練」などがあると、魂がそれに縛られてしまうとされています。こうした思いは、物理的なものだけでなく、感情的なもの――怒り、悲しみ、後悔、愛情――といった心理的な要素も含みます。
特に、突発的な事故や事件によって亡くなった場合は、自分の死を自覚できないこともあります。このとき、魂が「まだ生きているつもり」で日常を繰り返し、その場所から離れられないという話が伝えられることもあります。
また、遺された家族の強い悲しみや後悔も、魂の成仏を妨げる要素になると考えられています。たとえば「もっと〇〇してあげればよかった」と悔やむ気持ちや、「まだ一緒にいたかった」という思いが強すぎると、それが故人の魂に伝わり、旅立ちに影響を与えることがあるのです。
一方で、こうした執着や未練を「悪いもの」として避けるのではなく、向き合って和らげていくことが重要です。供養や祈りの場を通じて、少しずつ気持ちを整え、執着を手放していくプロセスこそが、成仏を後押しすることにつながると考えられています。
このように、成仏を妨げる執着や未練には多くの形があり、それを断ち切るには、亡くなった人だけでなく、生きている側の心の整理も大きな意味を持ちます。感情にふたをするのではなく、少しずつ向き合い、故人の思いを受け止めていくことが、魂を安らぎへと導く第一歩になるでしょう。
成仏を願う供養方法と現代の考え方
故人の成仏を願うための供養は、時代や地域によって形を変えながらも、今なお多くの人にとって重要な営みとなっています。供養というと、僧侶を呼んでお経をあげてもらう厳粛な儀式を思い浮かべるかもしれませんが、近年はもっと多様で柔軟な供養のあり方が受け入れられています。
本来の供養とは、亡くなった人の冥福を祈る行為全般を指します。代表的なものには、読経、焼香、仏壇へのお供え、年忌法要、納骨などがあり、いずれも「故人に想いを届ける」ことを目的としています。つまり、供養の本質は「形」ではなく「心」にあるといえるでしょう。
たとえば、忙しくて毎日仏壇に手を合わせることができないという方もいるかもしれません。しかし、通勤途中でふと故人を思い出したり、誕生日や命日にその人の好きだった料理を用意したりすることも、立派な供養の一つです。形式にとらわれすぎず、自分が無理なく続けられるスタイルで故人と向き合うことが、現代ではより重視される傾向にあります。
また、最近ではオンライン供養やリモート法要といった新しい形の供養方法も登場しています。遠方に住んでいても、インターネットを通じて僧侶の読経に参加したり、オンラインでお墓参りを依頼したりすることができるようになりました。こうしたサービスは、高齢化や核家族化が進む中で、供養の継続を支える手段として注目されています。
一方で、「きちんと供養しないと成仏できないのでは」と不安を感じる方もいますが、大切なのは気持ちがこもっているかどうかです。豪華な祭壇や大勢の参列者がいなくても、心からの祈りや感謝があれば、それは必ず故人に届くと信じられています。このように、成仏を願う供養の方法には多くの選択肢があり、必ずしも伝統的なやり方にこだわる必要はありません。自分と故人との関係、家族の状況、宗教的な考え方などに応じて、柔軟に選べることが現代ならではの供養のかたちです。大切なのは、形に惑わされず、「思いを伝えたい」という気持ちを持ち続けることだといえるでしょう。
亡くなった人が成仏するための正しい知識と供養に関するまとめ
以下のこの記事のポイントをまとめます。
- 成仏とは迷いを断ち仏の境地に至ることを指す
- 死後49日を経て魂は旅立つとされる
- 四十九日法要は成仏を祈る重要な節目である
- 戒名がなくても心ある供養があれば成仏できるとされる
- お経は魂を導く手段であり読経供養は成仏を助ける
- 成仏できない魂は霊として現世に残ると考えられている
- 虫になるという話は輪廻思想に基づく比喩的な表現である
- 執着や未練があると魂はあの世に進めないとされる
- 即身成仏は生きながら仏の境地に達する教えである
- 樹木葬でも供養の心があれば成仏に支障はない
- 現代では形式よりも心を込めた供養が重視されている
- 成仏を妨げる感情は遺族側の執着にも含まれる
- 新しい供養の形でも本質を守れば意味は失われない
- 成仏は故人だけでなく遺された人の心の整理にも関わる
- 亡き人への祈りや感謝が成仏への橋渡しとなる