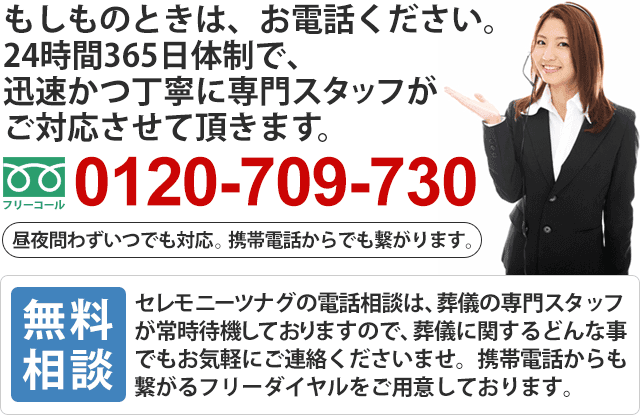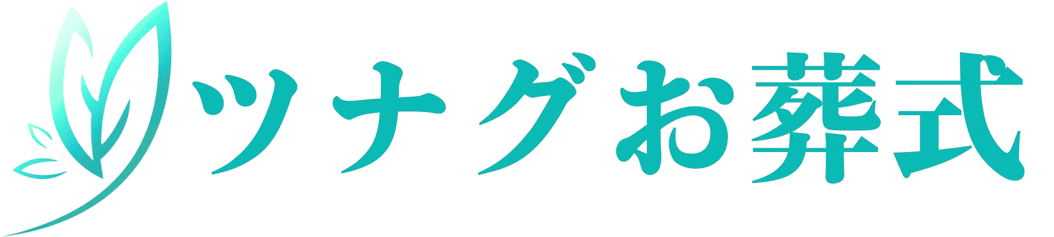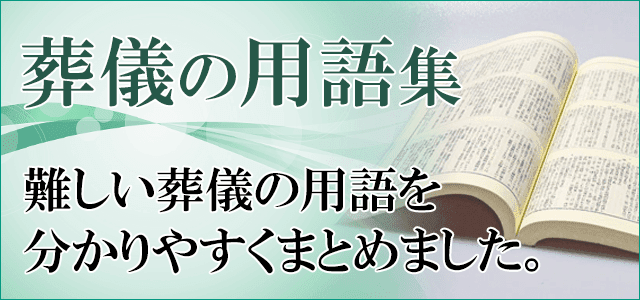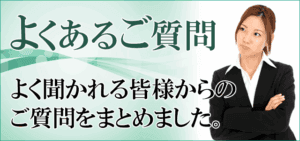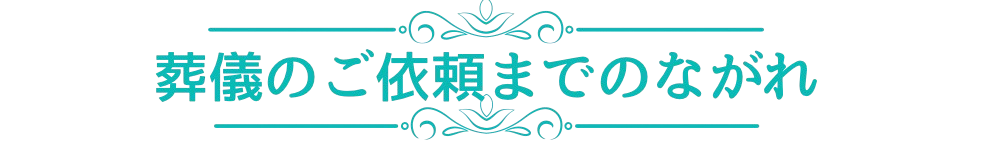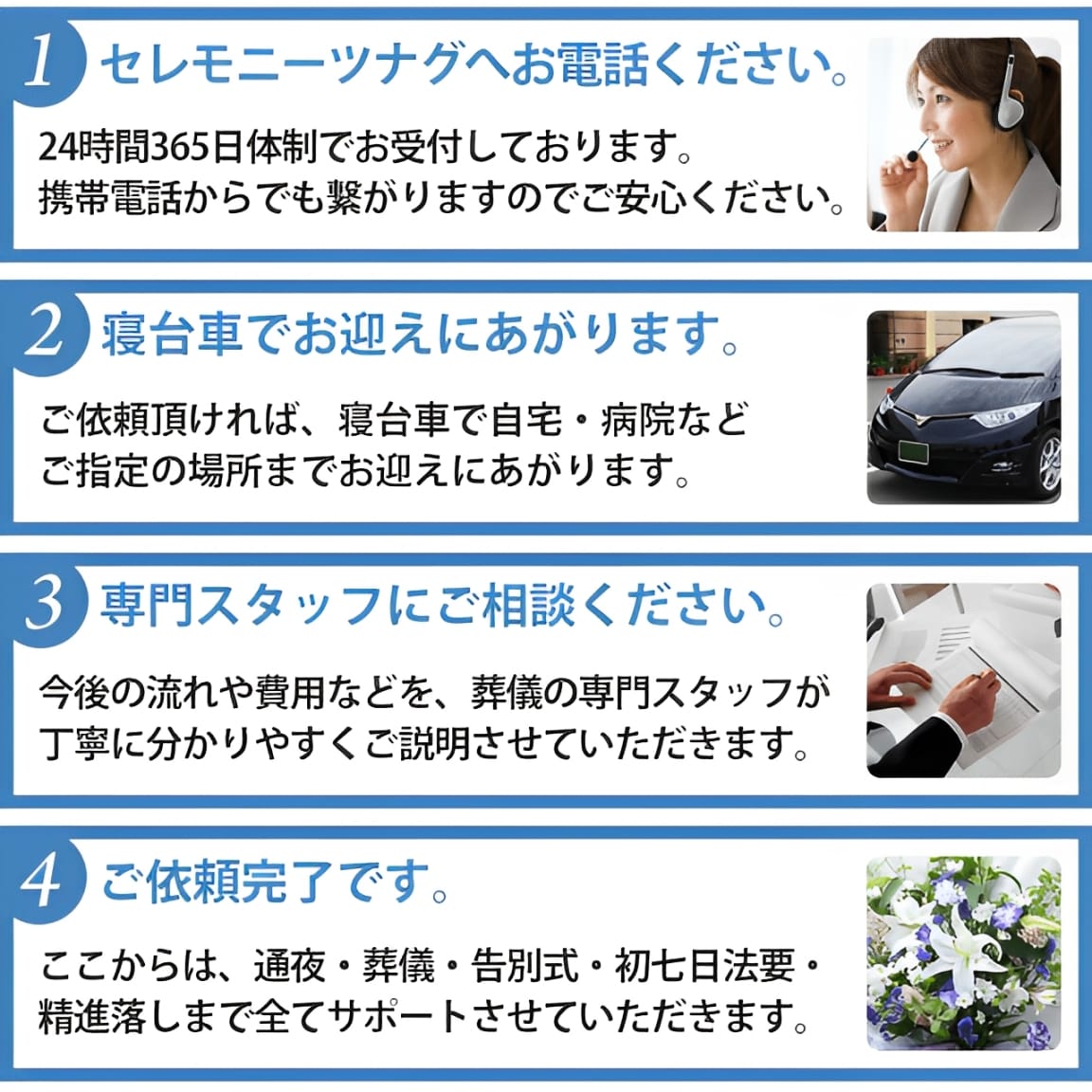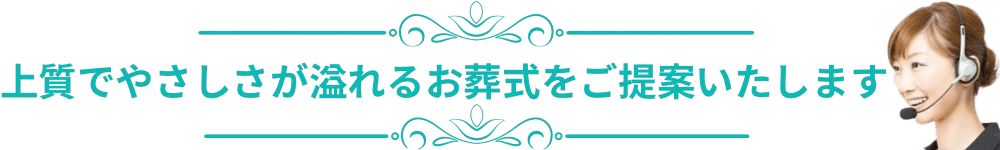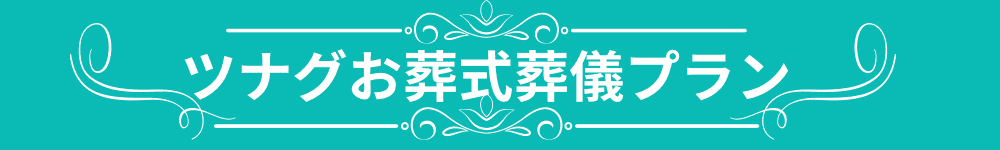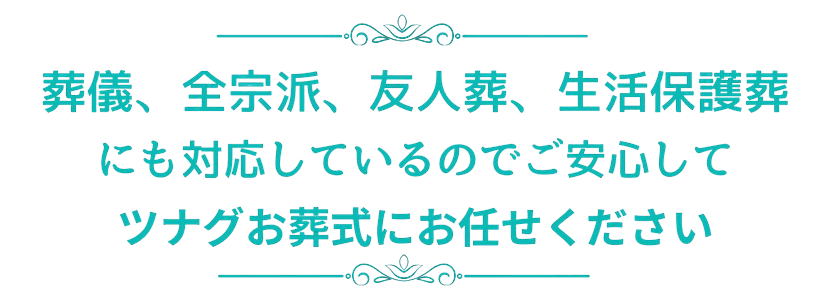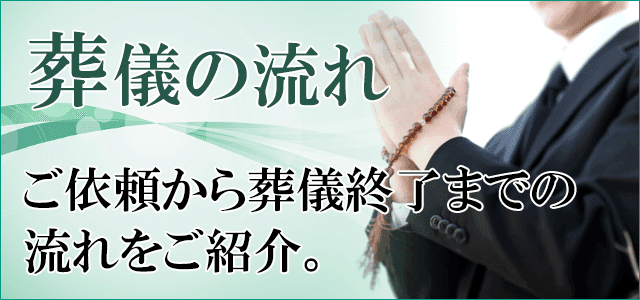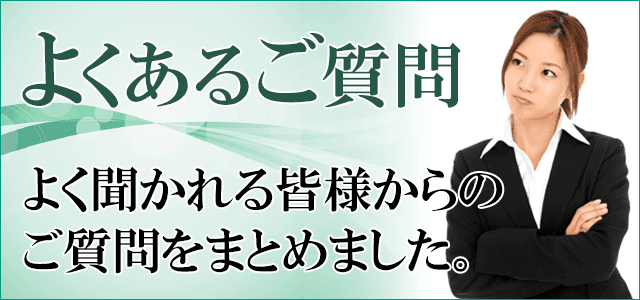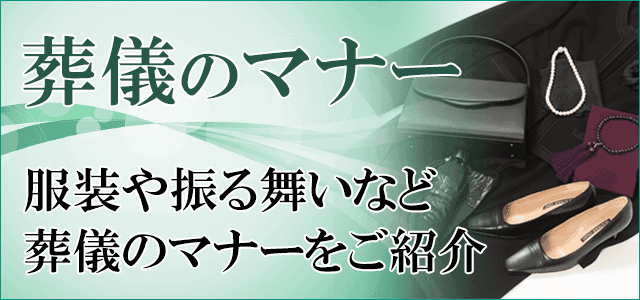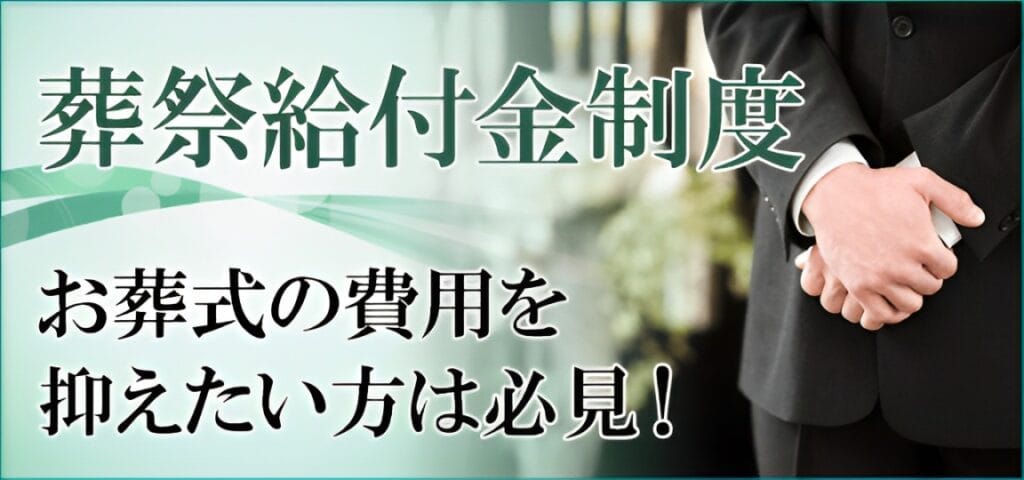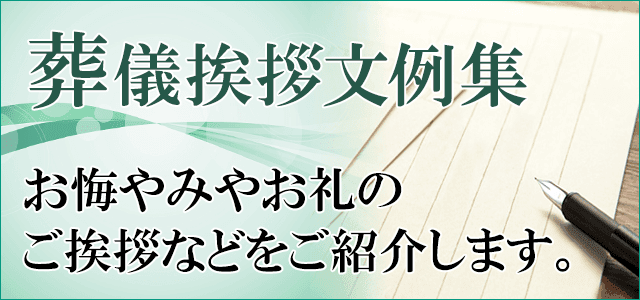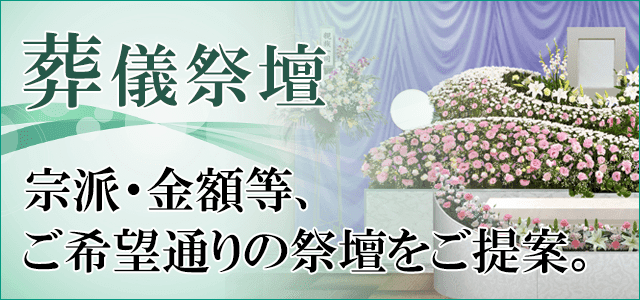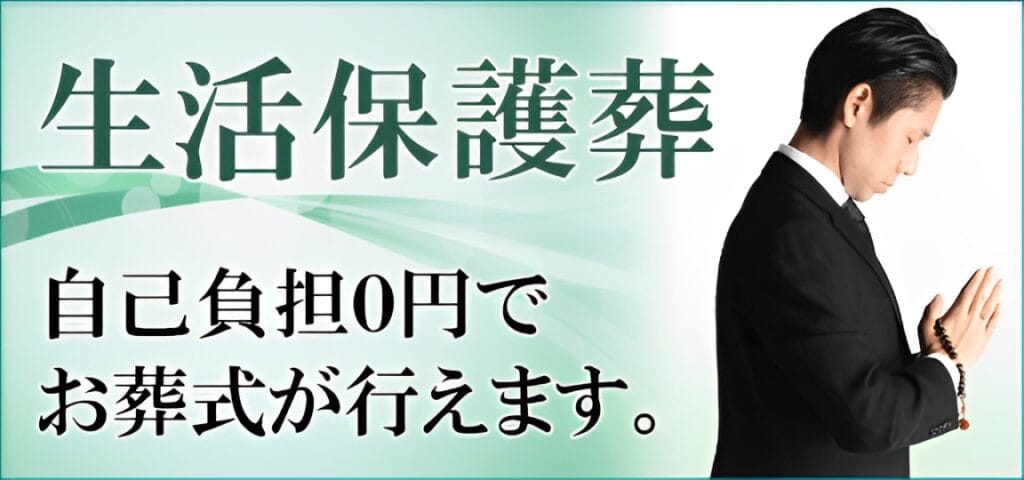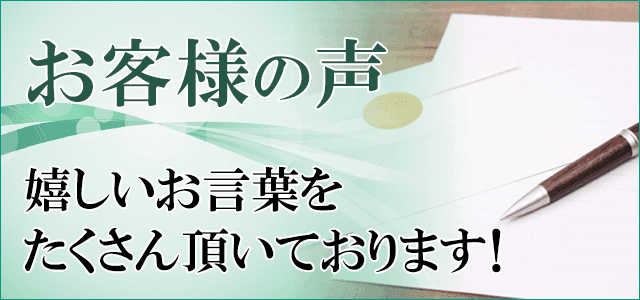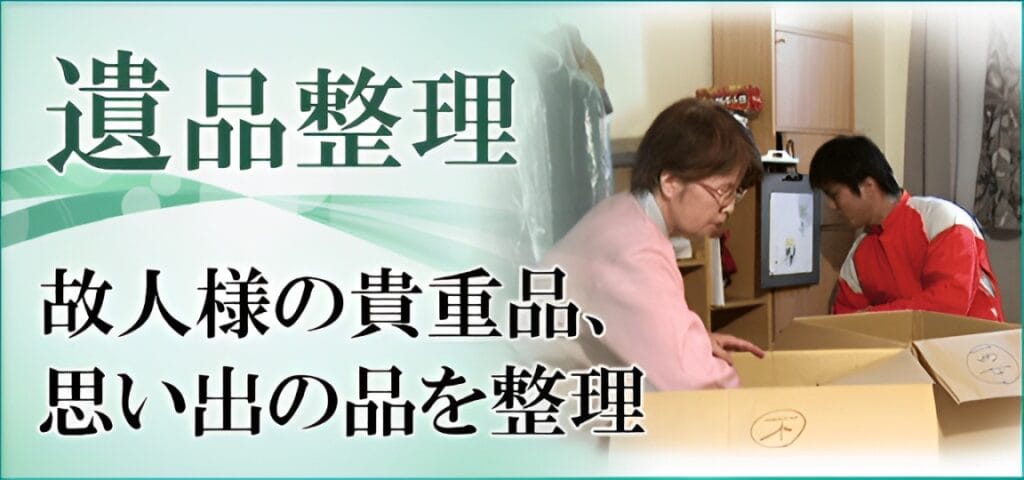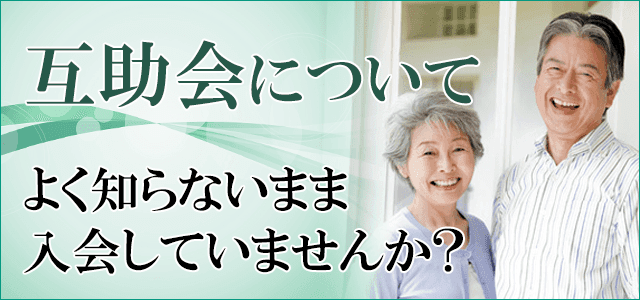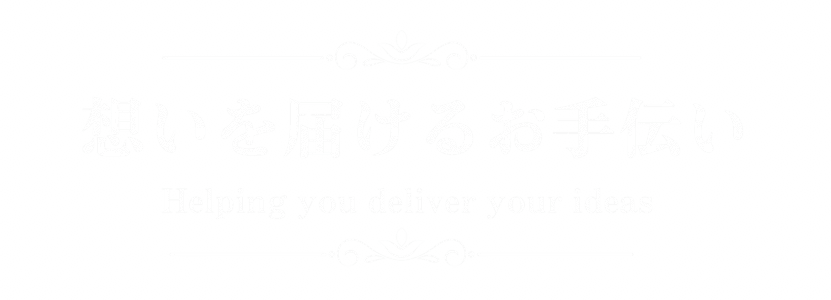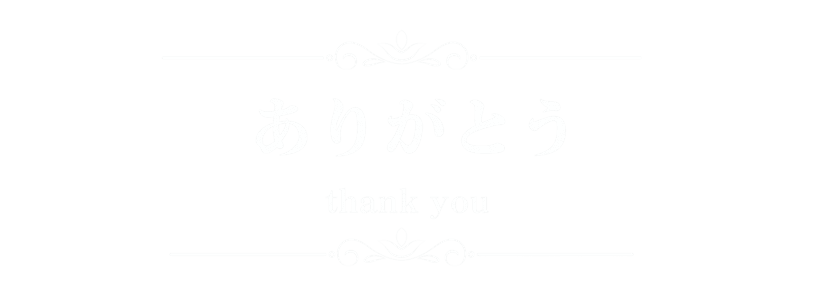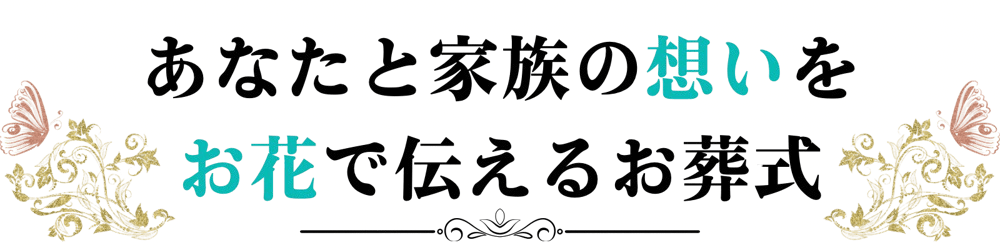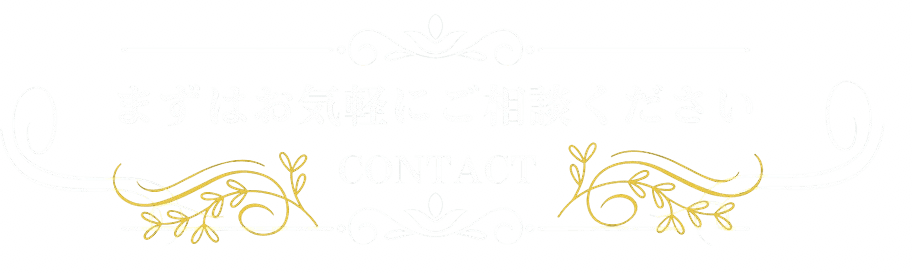葬儀用語集
日本の葬儀文化(主に仏教式)を中心に、神道、キリスト教、無宗教、地域差、現代トレンドを網羅し解説します。
葬儀用語集(50音順)
あ行
遺影(いえい)
意味: 故人の写真で、葬儀や法要で祭壇に飾る。
解説: 遺族が選んだ生前の写真(スナップやポートレート)を加工し、額縁に入れて祭壇中央に設置。笑顔やカジュアルな写真が増え、生前に準備する人も。葬儀後は仏壇や位牌と自宅に安置。神道やキリスト教では宗教的意味合いは薄い。
費用: 加工・額縁で1~5万円。
注意点: 写真は遺族の意向で選ぶ。背景や服装の加工も可能。
地域差: 特になし。
関連用語: 祭壇、仏壇。
一周忌(いっしゅうき)
意味: 故人の死後1年目の法要。
解説: 仏教の重要法要。親族が集まり、僧侶が読経、墓前や仏壇で行う。納骨が未了の場合、このタイミングで実施。会食や香典返し(引き出物)が一般的。三回忌(2年目)、七回忌(6年目)が続く。神道は「一年祭」、キリスト教は追悼ミサ。
費用: お布施5~20万円、会食・引き出物で10~30万円。
注意点: 参列範囲を事前決定。命日に近い週末が一般的。
地域差: 沖縄では盛大で親族全員が集まる。
関連用語: 四十九日、三回忌。
エンディングノート
意味: 生前に葬儀、遺産、希望を記すノート。
解説: 葬儀形式(家族葬、直葬)、連絡先、遺言簡易版、医療・介護希望を記載。遺族の負担軽減と故人の意志反映が目的。市販フォーマットやデジタル版(アプリ、クラウド)あり。法的効力はないが、遺言書と併用推奨。終活で普及。
市販ノート1,000~5,000円、無料テンプレートも。
注意点: 保管場所を家族に伝え、定期更新。
地域差: 都市部で普及。
関連用語: 遺言書、葬儀。
お布施(おふせ)
意味: 僧侶や宗教者への謝礼金。
解説: 仏教で読経や戒名授与の感謝として渡す。白封筒や奉書紙に「お布施」と書き、直接または葬儀社経由で手渡し。金額は宗派、戒名ランク、地域で異なる。神道は「玉串料」、キリスト教は「献金」。金額は明示せず寄付形式。
費用: 20~100万円以上。
注意点: 僧侶に金額を聞くのは失礼。菩提寺や葬儀社に相談。
地域差: 関西は高額傾向。
関連用語: 読経、戒名。
お盆(おぼん)
意味: 故人の魂が帰る夏の供養行事(7月または8月)。
解説: 仏教で、盆棚に提灯、供物(果物、素麺)を供え、僧侶が読経。迎え火・送り火の風習も。親族が墓参り。新盆は特に重要。神道は「祖霊祭」、キリスト教は類似行事なし。
費用: 供物・お布施で5~20万円。
注意点: 白提灯は新盆のみ。
地域差: 関東は7月、関西・九州は8月。
関連用語: 新盆、四十九日。
お別れ会(おわかれかい)
意味: 葬儀後に故人を偲ぶ非公式な集まり。
解説: 家族葬や直葬で参列できなかった人が別れを告げる。ホテルやレストランで食事会、音楽やスライドショーのセレモニーなど自由。宗教色を排除し、故人の趣味や人柄を反映。企業や著名人では大規模。無宗教葬と近い。
費用: 10~100万円以上(会場・規模による)。
注意点: 香典の有無を事前通知。
地域差: 都市部で増加。
関連用語: 家族葬、無宗教葬。
か行
火葬(かそう)
意味: 遺体を焼却し、遺骨にする。
解説: 日本ではほぼ100%火葬。葬儀や直葬の最終段階。火葬場で親族が見守り、収骨(骨壺に遺骨を収める)。「箸渡し」(2人で骨を拾う)が一般的。神道やキリスト教も火葬が主流。
費用: 5~15万円(自治体・施設による)。
注意点: 予約制で、都市部は待ち時間あり。
地域差: 関東は全骨、関西は一部収骨。
関連用語: 収骨、納骨。
家族葬(かぞくそう)
意味: 親族や親しい友人だけの小規模葬儀。
解説: 参列者を限定し、故人との時間を重視。仏教式、神道、無宗教など自由。費用は一般葬より安価。参列希望者への事前連絡が必要。後日「お別れ会」も。核家族化で増加。
費用: 50~100万円。
注意点: 参列範囲を明確に伝え、誤解を防ぐ。
地域差: 都市部で主流。
関連用語: 一般葬、直葬。
戒名(かいみょう)
意味: 故人に授けられる仏教上の名前。
解説: 仏の弟子となる象徴。位牌や墓石に刻む。2文字に信士・居士などのランク。浄土真宗は「法名」、日蓮宗は「法号」。神道やキリスト教は俗名や洗礼名。生前の「逆修戒名」も。
費用: 10~100万円以上。
注意点: 菩提寺と相談。ランクは予算で。
地域差: 都市部で高額傾向。
関連用語: 位牌、お布施。
香典(こうでん)
意味: 参列者が遺族に渡す金銭。供養や葬儀費用援助。
解説: 白黒水引の不祝儀袋に「御霊前」(葬儀時)、「御仏前」(四十九日以降)。金額は関係性で異なる(親族10~30万円、知人3~5万円)。新札は避け、奇数金額。香典返しは半額目安。神道やキリスト教でも類似。
費用: 袋は数百円~数千円。
注意点: 宗派確認(浄土真宗は「御仏前」)。香典辞退を事前確認。
地域差: 沖縄は高額香典。
関連用語: 香典返し、不祝儀袋。
香典返し(こうでんがえし)
意味: 香典のお礼として遺族が贈る品物。
解説: 仏教では四十九日後に「半返し」(香典の半額)。消耗品(お茶、タオル、洗剤)、食品(海苔、菓子)、カタログギフトが一般的。即日返し(葬儀当日に1,000~5,000円の品)も。神道やキリスト教でも同様。
費用: 香典総額の30~50%。
注意点: 香典金額を記録。地域の好みを考慮。
地域差: 関西は高級品、沖縄は実用品。
関連用語: 香典、礼状。
繰り上げ法要(くりあげほうよう)
意味: 初七日や四十九日を早く行う。
解説: 親族の都合や効率化で、葬儀当日に「繰り上げ初七日」が一般的。僧侶が読経、親族が焼香。四十九日も繰り上げ可。伝統では命日厳守だったが、都市部の多忙さで変化。神道やキリスト教では類似習慣なし。
費用: 葬儀と同時なら追加なし。別日で5~15万円。
注意点: 宗派や菩提寺に確認。親族の同意を。
地域差: 都市部で一般的。
関連用語: 初七日、四十九日。
献花(けんか)
意味: 葬儀や告別式で花を祭壇に供える。
解説: キリスト教葬や無宗教葬で一般的。仏教の焼香、神道の玉串奉奠に相当。白菊、ユリ、カーネーションを使用。無宗教ではカラフルな花も。司会者の案内で順番に。
費用: 葬儀費用に含まれる(1本100~500円相当)。
注意点: 作法を事前確認。
地域差: 特になし。
関連用語: 焼香、花祭壇。
さ行
祭壇(さいだん)
意味: 葬儀会場に設置する故人供養の台や飾り。
解説: 仏教は白木祭壇や花祭壇。神道は神饌を供える簡素な祭壇、キリスト教は十字架や花。花祭壇は故人の好みを反映。費用のかなりの部分を占める。レンタルや簡素なデザインも。
費用: 10~100万円。
注意点: 予算に応じた選択。遺影とのバランスを。
地域差: 関西は花祭壇が豪華。
関連用語: 遺影、花祭壇。
散骨(さんこつ)
意味: 遺骨を海や山に撒く供養。
解説: 自然に還る希望や墓維持の困難さから選択。海洋散骨が主流。専門業者が許可された場所で実施。法規制を遵守。遺族立ち会いか委託か選ぶ。無宗教や仏教、神道でも対応。
費用: 10~50万円。
注意点: 親族の同意必須。散骨後の供養を検討。
地域差: 都市部や沿岸部で増加。
関連用語: 納骨、手元供養。
四十九日(しじゅうくにち)
意味: 故人の死後49日目の法要。忌明け。
解説: 仏教で、魂が次の生に向かう節目。僧侶が読経、親族が集まる。納骨や位牌の仏壇安置。会食も。繰り上げや週末開催も。神道は「五十日祭」、キリスト教は追悼ミサ。
費用: お布施・会食で10~30万円。
注意点: 菩提寺と日程調整。香典は「御仏前」。
地域差: 沖縄は「七日七日」で毎週法要。
関連用語: 初七日、納骨。
死装束(しにしょうぞく)
意味: 故人が着る最後の衣装。通常は白い経帷子。
解説: 仏教は経帷子、頭陀袋、草履、数珠で旅支度。右前で着せる。神道は白装束、キリスト教は正装や白服。愛用の服も増加。副葬品は火葬場のルールで制限。
費用: 経帷子一式1~5万円。愛用品は追加なし。
注意点: 宗派や故人の希望を確認。
地域差: 特になし。
関連用語: 納棺、湯灌。
新盆(にいぼん/しんぼん)
意味: 故人の死後、初めてのお盆。
解説: 仏教で、魂が初めて帰る重要行事。盆棚に白提灯、供物を供え、僧侶が読経。親族が墓参り。盛大な法要や盆踊りも。神道は「祖霊祭」。
費用: 提灯5,000~3万円、お布施・供物で10~30万円。
注意点: 白提灯は1年限り。
地域差: 関西は「初盆」と呼び豪華。
関連用語: お盆、四十九日。
神葬祭(しんそうさい)
意味: 神道の葬儀。
解説: 故人を神として祀る。「穢れ」を清める清め塩や祓い儀式。通夜祭、葬場祭、火葬祭など。神職が執り行い、玉串奉奠や神饌供え。皇室や伝統家で選ばれる。
費用: 100~200万円。玉串料20~50万円。
注意点: 神道作法を事前確認。
地域差: 特になし。
関連用語: 玉串奉奠、仏教葬。
初七日(しょなぬか)
意味: 故人の死後7日目の法要。
解説: 仏教で、魂が裁きを受ける節目。現代では葬儀当日の「繰り上げ初七日」が一般的。僧侶が読経、親族が焼香。「七日七日」も地域で。神道は「十日祭」、キリスト教は類似なし。
費用: 葬儀と同時なら追加なし。別日で5~15万円。
注意点: 繰り上げは菩提寺に確認。
地域差: 沖縄で「七日七日」が強い。
関連用語: 四十九日、繰り上げ法要。
焼香(しょうこう)
意味: 香を焚いて故人を供養。
解説: 仏教葬儀の中心。参列者が抹香を香炉に落とす。宗派で回数や作法が異なる(浄土宗2回、曹洞宗2回で1回目は額に)。通夜、葬儀で順番に。神道は玉串奉奠、キリスト教は献花。
費用: 葬儀費用に含まれる。
注意点: 順番は親族から、親等順。
地域差: 特になし。
関連用語: 玉串奉奠、献花。
葬儀(そうぎ)
意味: 故人を悼み、魂を供養し、遺体を見送る儀式。
解説: 仏教、神道、キリスト教、無宗教など多様。仏教は通夜、葬儀、告別式。神道は神葬祭、キリスト教はミサ。家族葬や直葬も増加。宗教的儀式と社会的な別れの場。
費用: 一般葬100~200万円、家族葬50~100万円。
注意点: 宗派や地域慣習を確認。
地域差: 東日本は通夜、西日本は葬儀がメイン。
関連用語: 通夜、告別式。
直葬(ちょくそう)
意味: 通夜や告別式を省略し、火葬のみ。
解説: 費用や宗教儀式を抑えたい場合に選択。遺体を安置後、火葬場で親族が立ち会い、収骨。都市部で増加。伝統重視の地域や親族で抵抗も。後日法要やお別れ会を検討。
費用: 20~50万円。
注意点: 親族の理解を得る。
地域差: 都市部で主流。
関連用語: 家族葬、火葬。
た行
玉串奉奠(たまぐしほうてん)
意味: 神道葬儀で、玉串を神前に捧げる。
解説: 仏教の焼香に相当。参列者が榊の枝を祭壇に供え、二礼二拍手一礼。神と故人を繋ぐ象徴。神道の「穢れ」を清める厳粛な儀式。
費用: 葬儀費用に含まれる。
注意点: 作法を事前確認。
地域差: 特になし。
関連用語: 焼香、神葬祭。
手元供養(てもとくよう)
意味: 遺骨や遺灰を自宅で保管し供養。
解説: 墓や納骨堂に納めず、骨壺や小型容器(ペンダント、ミニ骨壺)に遺骨を自宅に安置。墓維持が難しい、故人を身近に感じたいニーズで増加。遺骨をアクセサリー(ダイヤモンド、ガラス)にするも。無宗教や仏教、神道で対応。
費用: 容器・加工で1~30万円。
注意点: 親族の同意と保管管理。散骨や納骨と併用も。
地域差: 都市部で増加。
関連用語: 散骨、納骨。
弔辞(ちょうじ)
意味: 葬儀や告別式で故人に別れの言葉を述べる。
解説: 親しい友人、上司、親族代表が故人の思い出や功績を語る。仏教、キリスト教、無宗教で一般的。手紙形式で3~5分。祭壇に供えることも。事前に遺族の許可を得る。
費用: なし(自作)。プロ依頼で1~5万円。
注意点: 長すぎる内容や不適切な話題を避ける。
地域差: 特になし。
関連用語: 告別式、弔電。
弔電(ちょうでん)
意味: 参列できない人が送る哀悼の電報。
解説: 葬儀や通夜に電報サービスで送る。定型文(「ご冥福をお祈りします」)やオリジナル。台紙や花付きも。遺族は読み上げるか祭壇に飾る。現代ではメールやSNSも。
費用: 1,000~5,000円。
注意点: 日時と会場を正確に。遅れると失礼。地域差特になし。
関連用語: 弔辞、香典。
通夜(つや)
意味: 葬儀前夜の儀式で、故人と最後の夜を過ごす。
解説: 仏教で僧侶が読経、参列者が焼香。元は一晩中だったが、現代は「半通夜」で2~3時間。通夜振る舞い(食事・酒)も地域で。神道は「通夜祭」、キリスト教は「前夜式」。
費用: 会場・飲食費で10~30万円(葬儀費用に含まれる)。
注意点: 参列者の都合で時間調整。
地域差: 東日本は通夜がメイン、西日本は葬儀重視。
関連用語: 葬儀、焼香。
な行
納棺(のうかん)
意味: 故人の遺体を棺に納める儀式。
解説: 仏教で、死装束を着せ、湯灌や死化粧後、親族が立ち会う。愛用品(副葬品)を入れるが、火葬場のルールで制限(金属不可)。納棺師が専門的に行うことも。旅立ちを整える儀式。
費用: 納棺師手配で5~15万円。
注意点: 副葬品は事前確認。遺族の意向を尊重。
地域差: 特になし。
関連用語: 死装束、湯灌。
納骨(のうこつ)
意味: 火葬後の遺骨を墓や納骨堂に納める。
解説: 四十九日や一周忌に行う。墓石の下に骨壺を納め、僧侶が読経。都市部では納骨堂や樹木葬も。散骨や手元供養も選択肢。永く供養する第一歩。
費用: 開眼供養やお布施で5~20万円。
注意点: 墓の管理費や後継者を考慮。
地域差: 都市部で納骨堂増加。
関連用語: 散骨、四十九日。
納骨堂(のうこつどう)
意味: 遺骨を保管する施設。
解説: 墓の代わりにビル型や寺院内の施設に骨壺を安置。ロッカー式、仏壇式、自動搬送式など。都市部で増加。契約期間(10~50年)や永代供養付きも。仏教、神道、無宗教に対応。
費用: 初期30~150万円、年間管理費5,000~2万円。
注意点: 契約内容を家族で共有。
地域差: 都市部で主流。
関連用語: 納骨、永代供養。
は行
仏壇(ぶつだん)
意味: 故人や祖先を祀る家庭の祭壇。
解説: 仏教で、位牌、遺影、仏像を安置し、線香や供物を供える。黒塗りや金箔の伝統型から小型モダン型まで。四十九日以降に設置。浄土真宗は金仏壇、曹洞宗はシンプル。神道は神棚、無宗教は写真で代用。
費用: 5~100万円。
注意点: 開眼供養が必要。宗派に合ったデザインを。
地域差: 特になし。
関連用語: 位牌、開眼供養。
不祝儀袋(ふしゅうぎぶくろ)
意味: 香典を入れる白黒水引の袋。
解説: 「御霊前」(葬儀時)、「御仏前」(四十九日以降)を表書き。中袋に氏名・金額を記入。新札は避ける。宗派で水引の色や形が異なる。コンビニや文具店で購入。
費用: 数百円~数千円。
注意点: 宗派確認(浄土真宗は「御仏前」)。
地域差: 特になし。
関連用語: 香典、御霊前。
ま行
御仏前(ごぶつぜん)
意味: 四十九日以降の法要で香典袋の表書き。
解説: 仏教で、故人が仏になる四十九日以降に使用。葬儀時は「御霊前」。浄土真宗は葬儀時から「御仏前」(即仏)。毛筆で丁寧に書く。
費用: 香典袋の費用に含まれる。
注意点: 宗派確認必須。
地域差: 特になし。
関連用語: 御霊前、香典。
御霊前(ごれいぜん)
意味: 葬儀や通夜で香典袋の表書き。
解説: 仏教で、四十九日までの魂が仏でない時期に使用。神道やキリスト教でも可。神道は「御玉串料」、キリスト教は「御花料」も。浄土真宗では使用しない。
費用: 香典袋の費用に含まれる。
注意点: 宗派確認。
地域差: 特になし。
関連用語: 御仏前、香典。
無宗教葬(むしゅうきょうそう)
意味: 宗教に依らない葬儀。
解説: 仏教や神道の儀式を省き、故人や遺族の意向で設計。音楽葬、思い出のスライドショー、お別れ会形式など。献花や黙祷で偲ぶ。宗教者を呼ばず費用抑えられるが、演出で変動。価値観の多様化で増加。
費用: 50~150万円。
注意点: 親族の理解を得る。法要の有無を決める。
地域差: 都市部で増加。
関連用語: 献花、お別れ会。
や行
永代供養(えいたいくよう)
意味: 寺院や霊園が遺骨を永続的に管理・供養。
解説: 後継者不在や墓維持が難しい場合に選択。合祀墓、個別墓、納骨堂形式。契約時に一括費用で寺院が法要や管理。仏教が主だが、神道や無宗教も増加。生前契約も。
費用: 30~200万円。
注意点: 合祀後は遺骨取り出し不可。契約を家族で共有。
地域差: 都市部で増加。
関連用語: 納骨堂、散骨。
湯灌(ゆかん)
意味: 故人の遺体を清める儀式。
解説: 伝統は親族が温水で拭くが、現代は専門業者がシャワーや入浴で清める。魂を清らかにする意味。納棺前に行い、死化粧も。宗派や地域で省略も。
費用: 5~15万円。
注意点: 遺族の希望を確認。
地域差: 特になし。
関連用語: 納棺、死装束。
ら行
礼状(れいじょう)
意味: 葬儀や香典のお礼の手紙。
解説: 香典、弔電、参列への感謝を伝える。葬儀当日の簡易礼状(印刷)や、四十九日後の香典返し同封の正式礼状。定型文や故人のエピソードを追加。メールやLINEも増加。
費用: 印刷礼状100枚で5,000~1万円。
注意点: 参列者全員に漏れなく。誤字や宛名ミスに注意。
地域差: 特になし。
関連用語: 香典返し、弔電。
炉前勤行(ろぜんごんぎょう)
意味: 火葬場で火葬前の短い読経。
解説: 仏教で、故人の魂を見送る最後の儀式。火葬炉前で僧侶が経を読み、親族が焼香。10~15分。宗派で経典が異なる。神道やキリスト教は黙祷や祈祷で代える。
費用: お布施3~10万円(葬儀と別の場合)。
注意点: 火葬場のスケジュールに合わせ簡潔に。
地域差: 特になし。
関連用語: 火葬、読経。
わ行
位牌(いはい)
意味: 故人の戒名や法名を記した木製の牌。
解説: 仏教で、仏壇に安置し魂を祀る。仮位牌(白木)は四十九日まで、本位牌(黒塗りや金箔)に替える。家族の歴史を繋ぐ。神道やキリスト教は写真や遺品で代用。
費用: 本位牌2~10万円。
注意点: 戒名と一致。仏壇のサイズに合わせる。
地域差: 特になし。
関連用語: 戒名、仏壇。
あわせて読みたい
葬儀のよくある質問
葬儀のよくある質問 葬儀に関するよくある質問をQ&A形式で解説した内容です。日本の葬儀文化を基に、一般的な質問から具体的な疑問まで幅広くカバーしました。 もし… ツナグお葬式では、適正価格の葬儀をモットーにより質の高いサービスを目差して日々取り組んでおります。
火葬式(直葬)・1日葬、家族葬の事から一般的なご葬儀、自宅葬に至るまで、可能な限りご親族様のご希望に添えるように努力していく所存でございます。ご相談がございましたらお気軽にご連絡下さいませ。