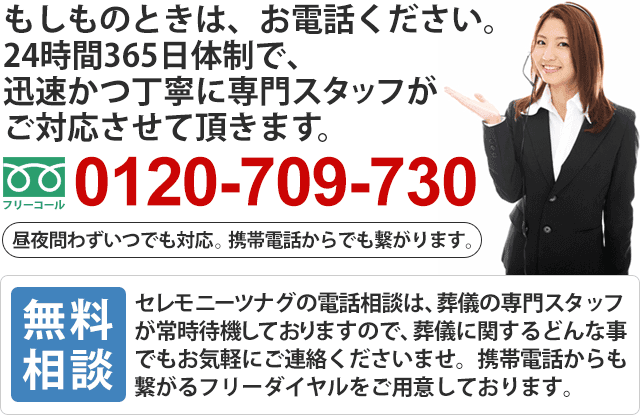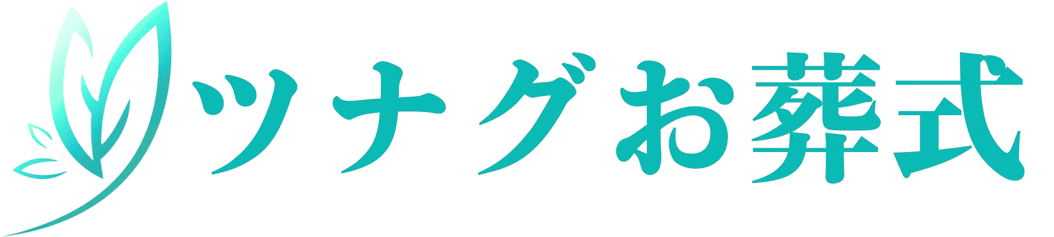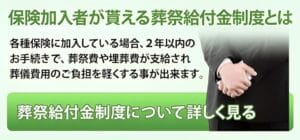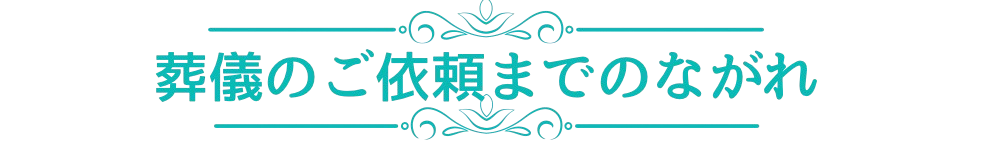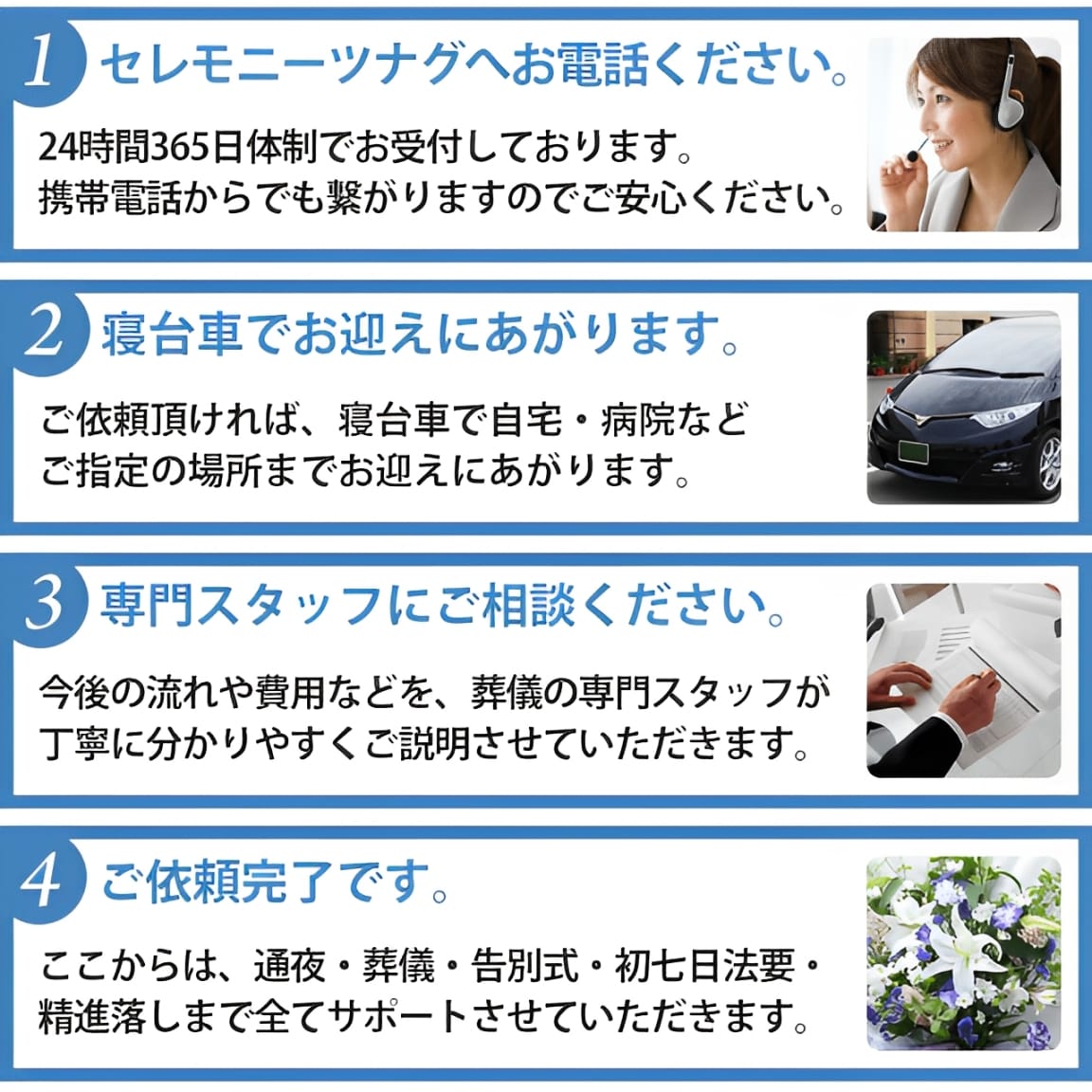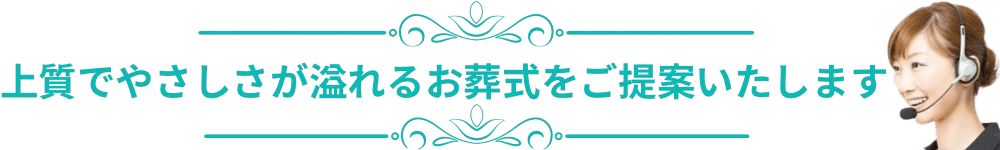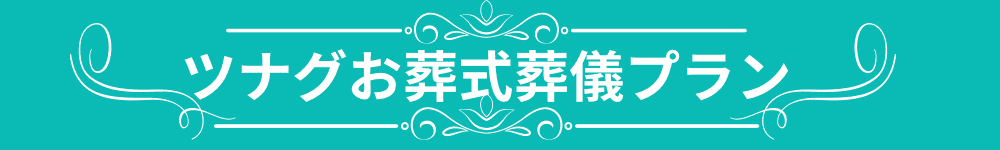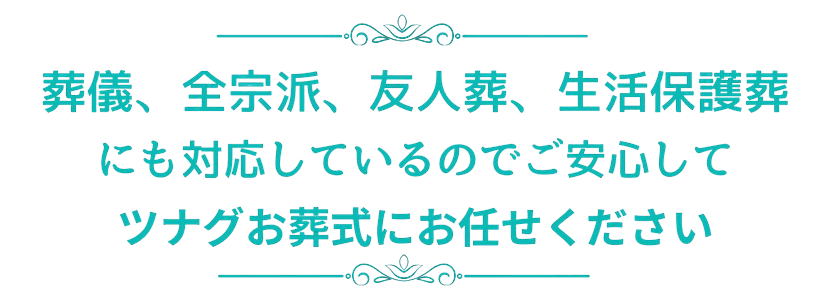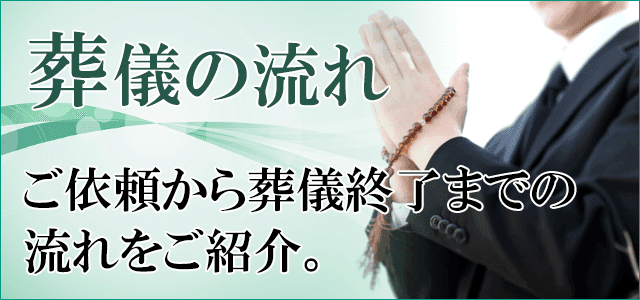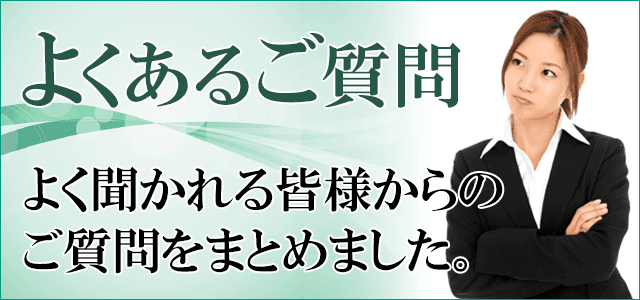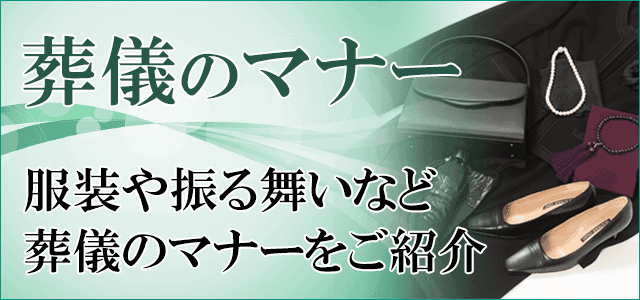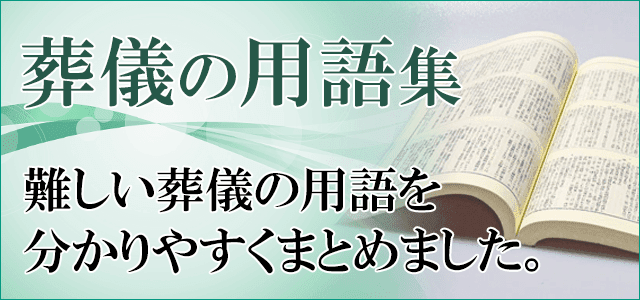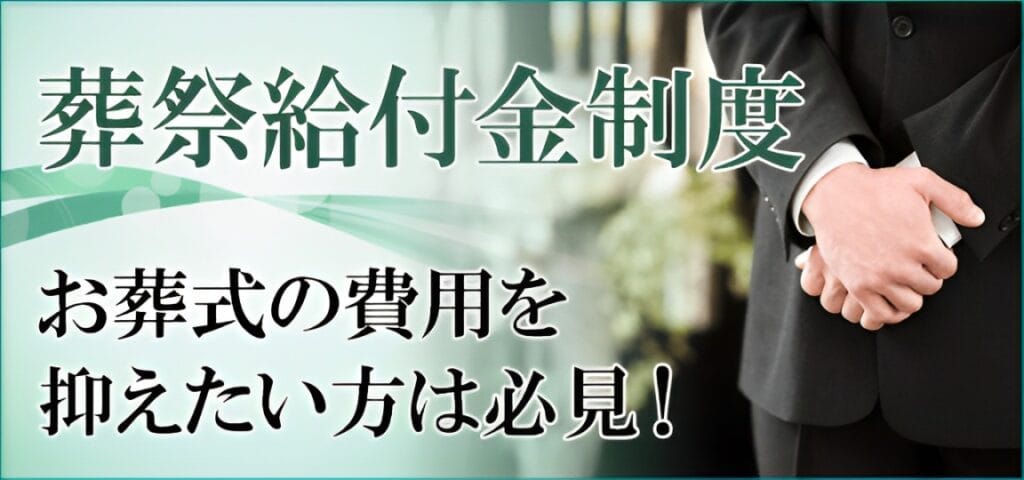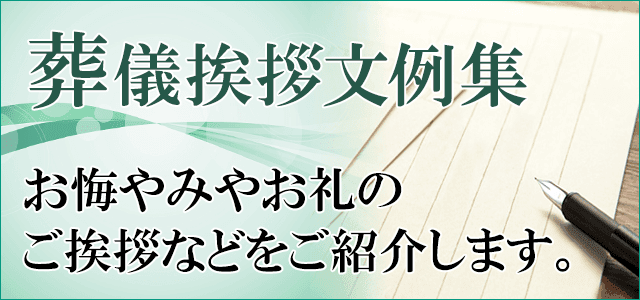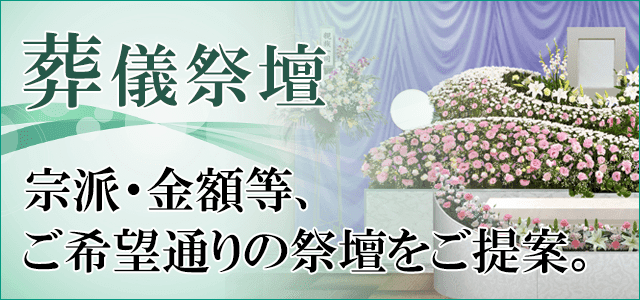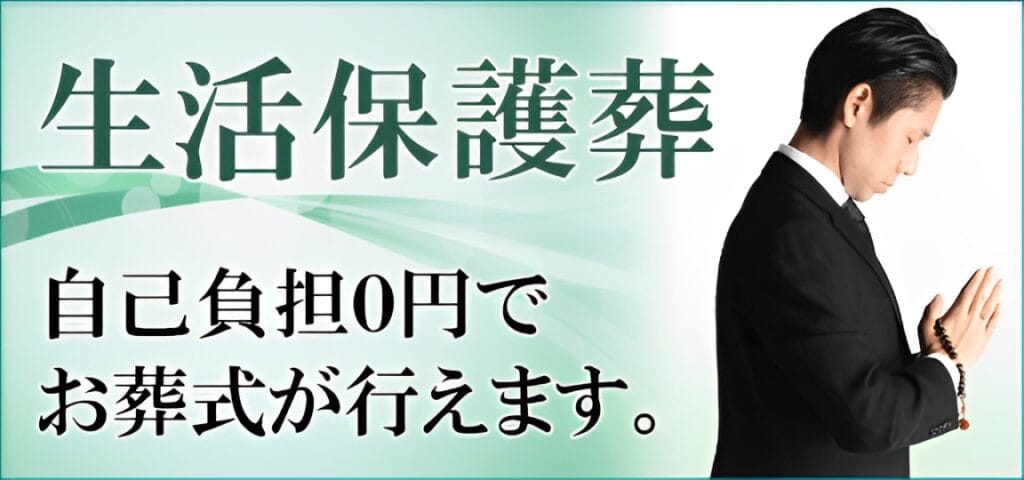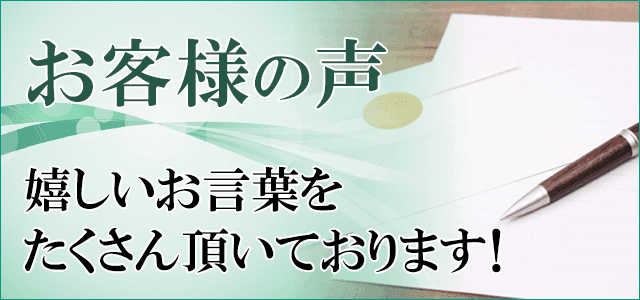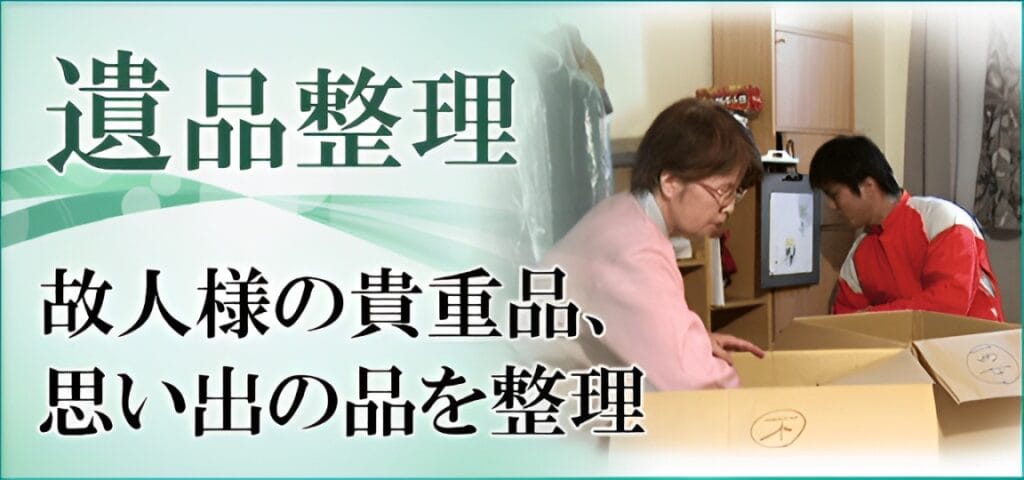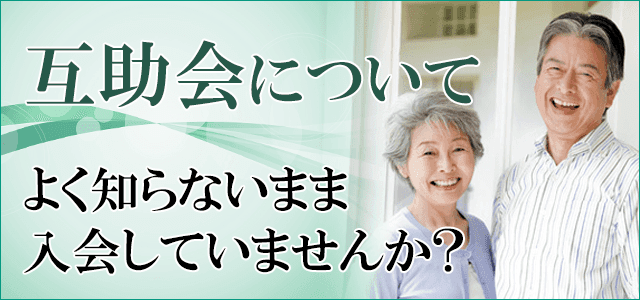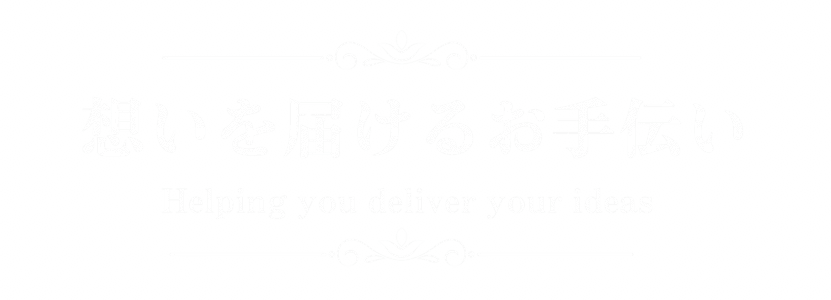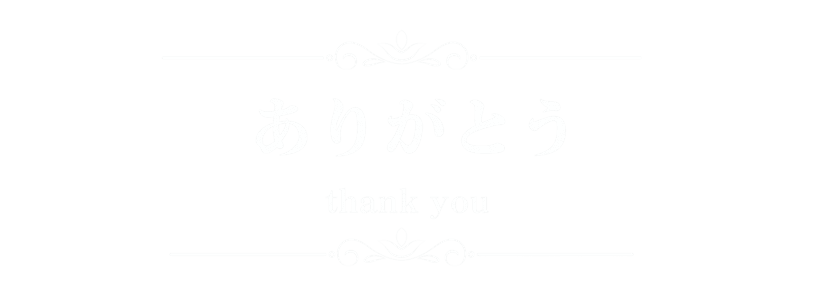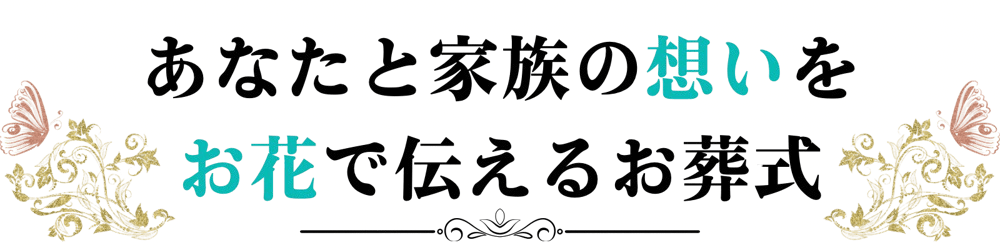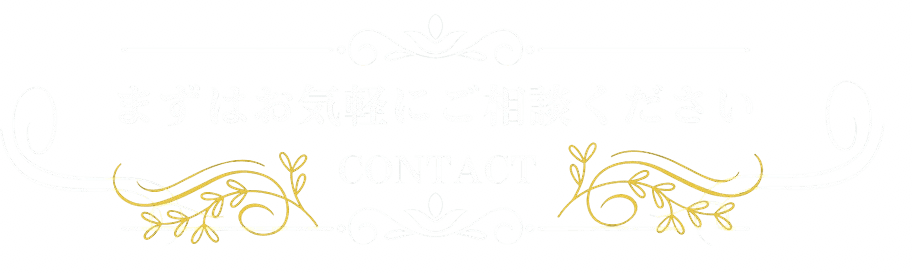料理のご案内

お葬式、葬儀の料理には、おもてなしの心と、悲しみを和らげ故人様を偲びながら思い出を語り合う場が必要であると弊社は考えます。
お気軽にお問い合わせいただければ、真心込めたお料理をご提供いたします。
お通夜料理
お通夜の後の席を、通夜振る舞いと呼び、故人様への供養とともに、弔問へのお礼のしるしとして設けられます。
地方によって習慣に違いがあります。料理を供する場合、人数が直前になるまで予想できないこともあって、盛り合わせの料理を大皿でとりわける形がよく見られます。
※写真はイメージです。

つつじ(Aセット) | 
あじさい(Bセット) |

サンドイッチ | 
おにぎりセット |

洋風オードブル | 
和風オードブル |

揚げ物盛り合わせ | 
お子様寿司セット |
葬儀、告別式のお料理(仕上げ料理)
火葬~お骨上げまでの待機中にお出しする料理です。
お通夜同様、対象は【ご家族・親族のみ】になります。
告別式に参列される人数をすぐに判断することは難しいと思いますので、お通夜の状況などを考慮してご判断くださいませ。

若葉膳 | 
羽衣膳 |

白梅膳 | 
時雨膳 |

常盤膳 | 
華かんざし |

お子様用:桜 | 
お子様用:菫 |
■ お料理は、保冷車でお届け致します。徹底した衛生管理のもと、安全に美味しくお召し上がり頂けるよう、お召し上がりの時間にあわせて調整させて頂いています。
■ 食事会場のセッティングから、配膳・後片づけまで行います。
■ お飲み物もご用意いたします。(ビール・焼酎・日本酒・ノンアルコールビル・ウーロン茶・ソフトドリンクなど)
- 家族葬の場合、料理を注文しない人もいますか?
お料理を注文されない方もいらっしゃいます。
火葬の間(約2時間)、ご家族で火葬場付近のレストランへ食事に行かれるか、斎場内の待合室にて休憩されています。
葬儀の料理について、わかりやすく丁寧に解説します。日本の葬儀における料理は、地域や宗教、宗派、参列者の規模などによって異なりますが、一般的には「通夜振る舞い」や「お斎(おとき)」と呼ばれる食事があります。これらの料理は、故人を偲び、参列者への感謝を表すとともに、コミュニティの絆を深める役割を果たします。以下に、葬儀の料理に関する目的、種類、特徴、具体例、注意点などを徹底的に解説します。
1. 葬儀の料理の目的と役割
葬儀における料理は、単なる食事提供以上の意味を持っています。主な目的は以下の通りです。
故人への供養
仏教では、故人の魂を慰め、供養するために食事を供える習慣があります。参列者が食事を共にする行為自体が、故人への敬意や供養の一環とされています。
参列者へのおもてなし
通夜や葬儀に参列してくれた方々への感謝の意を込めて、食事を提供します。特に遠方から来る参列者にとっては、食事は休息や交流の場ともなります。
コミュニティの絆を深める
葬儀は親族や地域の人々が集まる機会であり、食事を共にすることで悲しみを分かち合い、互いの絆を再確認します。
宗教的・文化的意義
宗派や地域の慣習に基づき、特定の料理や食材が選ばれることがあります。たとえば、仏教では精進料理が基本ですが、神道やキリスト教では異なるスタイルが見られます。
2. 葬儀の料理の種類
葬儀の料理は、大きく分けて以下のタイミングで提供されます。それぞれの特徴を解説します。
(1)通夜振る舞い
概要:通夜の後に参列者に振る舞われる食事。比較的軽食や簡単な料理が多く、立食形式や仕出し弁当が一般的。
目的:通夜に参列した人々への感謝と、故人を偲ぶ場を提供する。
形式
立食形式:ビュッフェスタイルで、寿司やオードブル、サンドイッチ、揚げ物などが並ぶ。カジュアルで参列者が自由に交流できる。
仕出し弁当:個別に用意された弁当を提供。準備が簡単で、持ち帰りも可能。
会席形式(まれ):高級な会席料理を出す場合もあるが、予算や規模による。
料理例
寿司(ちらし寿司、巻き寿司、にぎり寿司)
オードブル(サラダ、揚げ物、煮物)
サンドイッチやおにぎり
果物や和菓子
飲物:ビール、日本酒、焼酎、ソフトドリンク、ウーロン茶など。
特徴
準備が簡単で、参列者がすぐに食べられるものが多い。
地域によっては「通夜見ず(みず)」として、塩や水だけで済ませる簡素な形式もある。
肉や魚を避ける精進料理が基本の場合もあるが、現代では一般的な料理も多く見られる。
(2)お斎(おとき)
概要:葬儀・告別式の後や初七日法要の後に提供される食事。仏教の葬儀で特に重要視される。
目的:故人の供養と参列者への感謝を兼ねる。比較的正式な食事で、着席形式が一般的。
形式
会席料理:和食中心のコース料理で、季節の食材を使った品々が提供される。
精進料理:仏教の教えに基づき、肉や魚を使わず、野菜や豆類を中心とした料理。
仕出し弁当:お斎でも弁当形式が選ばれる場合がある。特に小規模な葬儀や家族葬で多い。
料理例
精進料理:ごま豆腐、こんにゃくの煮物、ひじきの炒め物、野菜の天ぷら、豆腐料理、きのこ料理など。
一般的な会席料理:刺身、天ぷら、煮物、焼き魚、ご飯、味噌汁、漬物、デザート(果物や和菓子)。
地域特有の料理:たとえば、関西では「ハリハリ鍋」や「精進寿司」、東北では「けんちん汁」など。
飲物:日本酒、焼酎、ビール、ソフトドリンクなど。お斎ではお酒を提供する場合も多いが、宗派によっては控えることも。
特徴
精進料理が基本だが、現代では肉や魚を含む料理も提供されることが多い。
格式高い雰囲気で、参列者が故人を偲びながらゆっくりと食事を楽しむ。
(3)法要時の料理
概要:初七日や四十九日、百か日、一周忌などの法要の後に提供される食事。
目的:供養と参列者へのおもてなし。
形式:お斎と似た形式で、会席料理や精進料理、仕出し弁当が一般的。
特徴
法要の規模が小さい場合は、家族や親族だけで簡素な食事となることも。
地域によっては「精進落とし」として、肉や魚を使った料理を出す場合もある(四十九日以降など)。
3. 葬儀の料理の特徴と注意点
葬儀の料理には、宗教や地域、参列者のニーズに応じた特徴や注意点があります。
(1)宗教・宗派による違い
仏教
精進料理が基本。特に浄土真宗や曹洞宗では、肉や魚を避けた料理が好まれる。
ただし、現代では一般的な和食や洋食も提供されることが多い。
浄土宗や真言宗では、精進料理にこだわらない場合も。
神道
精進料理の概念はなく、魚や肉を含む料理が提供される。
「神饌(しんせん)」の影響で、米や魚、野菜を使ったシンプルで清らかな料理が選ばれることも。
キリスト教
特に決まった形式はなく、洋食やビュッフェ形式が一般的。
肉や魚を使った料理が多く、ワインやジュースなどの飲物も提供される。
無宗教
自由な形式で、故人の好物や参列者の好みに合わせた料理が選ばれる。
洋食や中華など多様なメニューが見られる。
(2)地域による違い
関東:寿司や天ぷら、煮物など、比較的豪華な料理が提供されることが多い。通夜振る舞いは立食形式が一般的。
関西:精進料理が重視される傾向があり、こんにゃくや豆腐料理がよく出される。お斎は会席形式が多い。
東北:素朴な料理が多く、けんちん汁や山菜料理が登場することも。
九州:魚介類を多く使う地域では、刺身や海鮮料理が中心になる場合も。
沖縄:豚肉を使った料理や、独特の精進料理が見られる。地域特有の「重箱料理」が提供されることも。
(3)注意点
食材のタブー:仏教では「五辛(ごしん)」と呼ばれるニンニク、ネギ、ニラ、らっきょう、玉ねぎを避ける場合がある。また、殺生を連想させる肉や魚を避ける宗派も。
アレルギー対応:参列者の中にアレルギーを持つ人がいる場合、事前に確認して対応する。
量の調整:参列者の人数や年齢層に合わせて、適切な量を用意する。食べ残しが出ないよう配慮が必要。
予算:豪華な会席料理から簡素な弁当まで、予算に応じて選ぶ。一般的には1人当たり3,000円~10,000円程度。
時間帯:通夜振る舞いは夜遅くになることが多いため、消化に良い軽めの料理が好まれる。
4. 具体的な料理例とメニュー構成
以下は、葬儀の料理の具体的なメニュー例です。
通夜振る舞いのメニュー例(立食形式)
前菜:枝豆、冷やしトマト、酢の物
メイン:寿司盛り合わせ(ちらし寿司、巻き寿司)、天ぷら(エビ、野菜)、唐揚げ
サイド:サラダ、煮物(ひじき、里芋)
デザート:フルーツ盛り合わせ、和菓子
飲物:ビール、日本酒、ウーロン茶、ジュース
お斎のメニュー例(精進料理の会席形式)
先付け:ごま豆腐、わさび添え
椀物:きのこ汁、豆腐と三つ葉の清汁
煮物:こんにゃく、里芋、昆布の煮物
揚げ物:野菜の天ぷら
焼き物:焼き豆腐、椎茸の焼き物
ご飯:白米、または五目ご飯
香の物:漬物盛り合わせ
デザート:水ようかん、季節の果物
飲物:緑茶、ウーロン茶
お斎のメニュー例(一般的な会席料理)
先付け:季節の小鉢(胡麻和え、酢の物)
刺身:マグロ、タイ、ハマチ
焼き物:焼き魚(サバ、鮭)
煮物:筑前煮、茶碗蒸し
揚げ物:天ぷら盛り合わせ
ご飯:白米、またはちらし寿司
汁物:味噌汁、吸い物
デザート:フルーツ、羊羹
飲物:日本酒、ビール、ソフトドリンク
5. 葬儀の料理を準備する際のポイント
葬儀の料理を準備する際、以下のポイントを考慮するとスムーズです。
葬儀社との連携
多くの場合、葬儀社が提携する仕出し業者やケータリングサービスを手配してくれる。事前に予算や人数、料理の希望を伝える。
精進料理やアレルギー対応が必要か確認する。
会場の手配
自宅、斎場、寺院、ホテルなど、どこで食事を提供するかを決める。会場の広さや設備に応じて、立食か着席かを選択。
コロナ禍以降は、持ち帰り用の弁当を用意するケースも増えている。
参列者のニーズを考慮
高齢者が多い場合は、消化に良い柔らかい料理や小分けのメニューを。
子供がいる場合は、子供向けの軽食やアレルギー対応食を用意。
予算の設定
通夜振る舞い:1人当たり3,000円~5,000円
お斎:1人当たり5,000円~15,000円
法要:1人当たり3,000円~10,000円
予算に応じて、仕出し弁当やケータリングを選ぶ。
地域の慣習を確認
地域によっては「出棺前におにぎりを食べる」「塩を振る舞う」などの独特な慣習がある。事前に親族や地域の年長者に確認。
6. 現代のトレンドと変化
近年、葬儀の形態が多様化する中で、料理にも変化が見られます。
家族葬の増加
小規模な葬儀では、親族だけで簡素な食事を提供するケースが多い。仕出し弁当やオードブルが人気。
持ち帰り用の弁当や個食パックが増加。
多様な料理スタイル
洋食や中華、エスニック料理を取り入れるケースも。特に無宗教やキリスト教の葬儀で多い。
故人の好物や思い出の料理を提供する「パーソナライズドメニュー」も増えている。
コロナ禍の影響
感染症対策として、個別包装の弁当やテイクアウト形式が普及。
オンライン参列が増えたため、料理の提供自体を省略するケースも。
エコ意識の高まり
食べ残しを減らすため、少量多品目のメニューや、環境に配慮した容器を使用する業者が増えている。
7. よくある質問と回答
- 精進料理と普通の料理、どちらを選ぶべき?
宗派や地域の慣習による。仏教の厳格な宗派(例:曹洞宗)では精進料理が推奨されるが、現代では一般的な料理も広く受け入れられている。親族や葬儀社に相談を。
- 料理の量はどのくらい用意すべき?
参列者の人数の8~9割程度を目安に。急な増減に備え、追加注文が可能な業者を選ぶと安心。
- お酒は提供すべき?
宗派や地域によるが、通夜振る舞いやお斎でお酒を提供することは一般的。ただし、浄土真宗などお酒を控える宗派もあるため、事前確認を。
- 子供や高齢者向けのメニューは必要?
参列者に子供や高齢者が多い場合、柔らかい料理やアレルギー対応食を用意すると喜ばれる。業者に相談して対応可能か確認。
8. まとめ
葬儀の料理は、故人への供養、参列者への感謝、コミュニティの絆を深める重要な要素です。通夜振る舞いやお斎を中心に、精進料理や一般的な会席料理、仕出し弁当など、形式や内容は多岐にわたります。宗教や地域の慣習、参列者のニーズ、予算に応じて適切な料理を選ぶことが大切です。葬儀社や仕出し業者と連携し、事前に詳細を打ち合わせることで、故人を偲ぶふさわしい食事が提供できます。
西宮市、芦屋市の葬儀、家族葬はツナグお葬式にお任せください。
ツナグお葬式では、適正価格の葬儀をモットーにより質の高いサービスを目差して日々取り組んでおります。
火葬式(直葬)・1日葬、家族葬の事から一般的なご葬儀、自宅葬に至るまで、可能な限りご親族様のご希望に添えるように努力していく所存でございます。ご相談がございましたらお気軽にご連絡下さいませ。
あわせて読みたい
葬祭給付金制度とは?わかりやすく徹底解説します。
葬祭給付金制度 日本における葬祭給付金制度は、故人の葬儀費用の一部を軽減するための公的な支援制度であり、国民健康保険や社会保険、後期高齢者医療制度、労災保険、…
あわせて読みたい
兵庫県西宮市の対応葬儀場、施設一覧
遠方から参列の方にも配慮し、交通至便な葬儀場や宿泊可能な葬儀場などを選定し、葬儀内容に見合った葬儀場をご案内させていただきます。ご自宅やお寺・公民館、集会所…